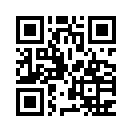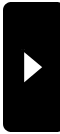2006年10月30日
日没の京都タワー
西山に沈む夕陽と京都の町並みに、京都タワーのシルエットが浮かんでいます。
みるみるうちに太陽が沈んでいくので、みな清水寺の仁王門の横で立ち止まり、静かな感嘆の声があたりに広がりました。
2006年10月30日
秋の清水寺
夕方、仕事で清水寺の方へいくと、ちょうど日が沈む間際で夕日に仁王門が朱く染まっていました。
2003年に修復した仁王門に比べると朱の色がくすんで見えますが、西門もなかなかのものです。
ばんばん写真を撮っていたら修学旅行の高校生男子4人組に写真を頼まれました。やすうけあいすると、「僕のもいいですか?」と4人がそれぞれ自分のカメラで撮って欲しいというので、西門をバックに四つのカメラで4枚の写真を撮りました。
よっぽど隙があったのか、そのあと中国のひと(らしい)にも写真を頼まれました。やれやれ・・・。
清水寺は11月11日(土)~12月3日(日)の間、夜間ライトアップされます。
そういえば清水寺は、「新・世界の七不思議」というものの最終候補に選ばれたと先日、報道されたばかりです。
■清水寺HP
■清水寺門前会HP
■the New 7 Wonders of the World HP
2006年10月30日
ジョロウグモの季節
今日は息子の通う保育園のバザーで、昼前から保育園にいき、ビールを飲みました。日射しが暑いくらいの一日でした。
保育園の前の坂道にジョロウグモが大量に発生していました。坂道の東側に背の低い街路樹が植えてあって、その木の上の方の枝や街灯を利用して、坂道の下からずっと並ぶようにアミが張ってあります。大きいアミは直径が1メートル以上ありそうです。
アミの真ん中にクモが逆さになって獲物を待ち構えています。黄色の模様がいかにも妖しげなこのクモの名はコガネグモとばかり思っていたのですが、記事を書くためにネットで調べると、どうもジョロウグモのようです(コガネグモは腹部が黄色と黒の縞模様になっています)。
子どもの頃から馴染みのクモで、よく木の枝でアミと一緒に絡めとるようにつかまえて遊びました。お尻から糸を引っ張り出して、木の枝に巻いていくと、いくらでも糸が伸びてきて不思議な感じがしました。ドラえもんのポケットみたいに底なしに思えて、それでちょっと怖いような気持ちになりました。
そういえば、数年前に大阪府南部に上陸したセアカゴケグモの生息が京都でも確認されました。宇治や伏見で数百匹が駆除されたということです。
■ジョロウグモ Wikipedia
■コガネグモ Wikipedia
2006年10月29日
自転車と秋の空。
息子といっしょだと近くの公園まで歩いて15分ほどかかっていました。途中でだっこをせがまれたりして、なかなか大変だっのですが、自転車だとずいぶん楽です。
自転車はよっぽどうまが合うのか、買ってまもないのにかなり乗りこなしています。三輪車にてこづったのがうそみたいな話です。
実は三輪車にもろくに乗れない息子に自転車なんて、まだまだ早いと思っていたのに、はやくも玉をとりたいと思っています。公園とかに行き、息子とそうかわらない小さな子が玉なしの自転車に乗っているのを見ると、ちょっと気になります。
あっ、て思い自転車の乗っている子をしばらく見ていると、その子と目があったりして、恥ずかしいです。
子どもの方から自発的に外したいという風な気持ちになるのを待ったほうがいいのでしょうか?
ボクが玉なしの自転車に乗れるようになったのはたぶん5〜6才位だったはずです。突然、バランスがうまくとれるようになり、まっすぐに走れるようになった喜びと驚きの感覚、壁をひとつ越えた強い達成感とともに、自転車に乗る自分自身を上から俯瞰するような記憶が微か残っています(というか突然、憶い出しました)。
車庫の前の道路、黄色い自転車。誰かに手伝ってもらっていたはずなのに、いったい誰だったのか、うまく憶い出せません・・・。
自転車の向こうに青い空と秋の雲が高く広がっていました。
2006年10月27日
獺祭書房にて。
いつもコメントをいれてくれるdrac obのブログで紹介されていた「獺祭書房」へ行ってきました。ちょっと近くへ寄る用事があったので、今出川室町から北の方へいくと西側にあるマンションの一階にありました。
ぐるっと見渡して、本を2冊購入しました。
「ベータ2のバラッド/サミュエル・R・ディレイニー他」
国書刊行会の“未来の文学”の第二期シリーズ。ニューウェーブSFの傑作アンソロジー。以前にも書いたことがあるが、ボクはニューウェーブに弱いのだ。
「オン・ザ・ボーダー/中上健次」
中上健次のエッセイ+対談集。対談は坂本龍一、栗本慎一郎、ビートたけし、そして超レアな村上春樹との対談。800円でした。
獺祭書房の屋号の由来は以下の通りです。(drac obさんのブログから引用)
獺(かわうそ)は、捕獲した魚を食べる前に岸辺に並べ置く習性を持つ。その様子になぞらえ、古来中国では詩作する人が机の周りに参考書籍を広げ散らすことを獺祭という。晩唐の詩人李商隠は、自らを獺祭魚と号し、広く故事を援用しつつ錯綜した時代の事蹟を詩に定着した。
カワウソを漢字で書くとなかなか恰好いいな。ちなみに「だっさいしょぼう」と読みます。
獺祭書房はこじんまりとして店内は明るく、ボク好みの本も多く並んでいました。ほかにも数冊気になる本があったので、近いうちにまた行ってみたいと思います。
2006年10月25日
ジム・ジャームッシュと古文書返却の旅

少し前のことだが、みなみ会館でジム・ジャームッシュ監督の「ブロークン・フラワーズ 」を観た。
ビル・マーレイが演じる主人公のもとに、実は息子が存在するという差出人不明の手紙が届く。心当たりがあるのは、かって彼が多くの恋愛を楽しんだプレイボーイだったからなのだが、相手が誰なのかまったく見当がつかない。気ままな生活を送る彼は特に頓着する様子もないのだが、おせっかいな隣人にそそのかされて、昔の彼女と息子を探す旅にでる。
元カノをシャロン・ストーンやジェシカ・ラングらの豪華女優陣が演じているというのが、この映画の売りのひとつだったのだが、ボクが観た理由は、やはりジム・ジャームッシュが監督だったからだ。
しかしネット検索で昔の彼女の居場所を探しあて、旅を続ける映画はまさに監督が得意とするロード・ムービーなのだけれども、あまりにこなれた感じがして、平坦な印象しか残らなかった。
ところで先日、読み終わった本の最後に「舞踏会の手帖」という映画のエピソードが書いてあって、粗筋としてこう書かれていた。
“中年をすぎた女主人公が、華やかだった若いころの舞踏会で会った男性たちを当時の手帳をたよりに探し出し、めぐり会う話で、美しく魅力的だった青年たちの、みじめに老いたなれのはてを知って、女主人公が暗い想いに沈む、悲しく淋しい印象の映画だった。”
ネットで調べると、フランスの古い映画で、DVD化もされている。ボクは知らないのだけど、わりと有名な映画みたいだ。
で、なんか話が似ているねというのが結論ではない。
そのエピソードが書いてあったのは2004年に亡くなった網野善彦の「古文書返却の旅」という新書だ。
著者が所属していた研究所が、戦後の混乱期に収集した日本各地の多くの古文書を、40年の歳月をかけて調査・返却を果たした顛末記だ。
戦後間もない頃、明治以前の民衆の暮らしを調べるために、研究所員たちは全国の漁村を巡り、村の地主らから土蔵に眠る古文書を借りうけた。その際、借用書を書いていながら、研究所の閉鎖などもあって持ち主に返されないまま古文書は研究者の自宅や新しい勤務先である大学の倉庫の奥に埋もれてしまう。返却を求める強い督促があっても、詳しく調べられることがなく年月が過ぎていく。
そして研究所の所長が死の間際に、「あとのことはよろしく頼む」と著者に後を託すのである。
著者は古文書返却の旅に出ることを決意し、様々な困難を乗り越え、古文書の本来の持ち主を探しあてるのだ・・・。
返却した先でひどく怒られると思っていたら、返却してくれたことを素直に喜ばれ、実はまだこんなのがありましたと差し出され、新たな古文書を発見する。なかには障子の裏紙として使用されているのを一枚づつはがしたりもする。古文書を返却するのと同時に、再調査もはじめる始末で、返却が片付かないうちに仕事がどんどん増えるばかりで、たいへんそうな様子が多彩なエピソードとともに描かれている。
ロードムービー的要素が満載なのですが・・・。
ジム・ジャームッシュが映画化しないかなと思う次第です。古い土蔵や古文書、さびれた漁村なんか「ストレンジャー・ザン・パラダイス」みたいに白黒で撮ればきっといい塩梅に違いないです。
あっ、監督はアキ・カウリスマキでもいいかもしれません。
■ブロークン・フラワーズHP