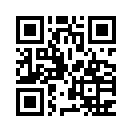2011年05月30日
台風とモンカゲロウ

まだ5月だというのに台風が接近して京都市内でも土曜から日曜にかけて100ミリを超える雨が降りました。増水の様子を見に行くと、賀茂川と高野川が合流する賀茂大橋の橋の上で、雨を避けているモンカゲロウを発見しました。
黒くて丸い大きな眼がかわいい奴です(モンカゲロウってこんなに大きな眼だったかな?)。灯篭の小さな屋根の下で雨を凌いでいたのでしょう。
しかし、そのすぐ上では蜘蛛の巣に絡まった別の個体もあって、命のやりとりがされています。たった数日の命なのにはかないものです。

2011年05月28日
『ストリート・キングダム/地引雄一』
『ストリート・キングダム〜東京ロッカーズと80'sインディーズシーン〜/地引雄一』(K&Bパブリッシャーズ)を読了。
69年生まれの僕は東京ロッカーズが盛り上がっていた70年代の後半はまだ半ズボンをはいて虫採りに夢中になって走り回っていた小学生だった。それから10年経って大学生になった頃、宝島でそんなムーブメントがあったことを知った。フリクションとかリザードとか興味はあったけど、日本のバンドより洋楽の方に惹かれていたので、音源を探すこともなかった。
この本を買ったのは、そのフリクションやリザードやS–KENらの未発表ライブのDVDが付いていたからなのだが、それよりも300ページの本の1/3を占める当時の写真の方がずっと素晴らしく、音はわからなくても、当時の熱を感じることができる。それはライブシーンの写真よりも、なんでもないスナップ写真の方が鮮明だ。
東京ロッカーズの真ん中にいた世代は、それ以前から音楽活動をしていたのだが、いったん挫折を経験した後にパンクと出会っている。挫折を味わった苦さと、それでも音楽しかないという強い決意のようなものがその眼差しから伝わってくる。
東京ロッカーズと呼ばれたムーブメントはほんの数年で終わったのだが、そのシーンに感化された恐れを知らない若者たちにその熱は受け継がれインディーズブームで一気に爆発するのだ(そして資本に取り込まれた末にバブル崩壊と共に瓦解することになる)。
テキストはその歴史(特に勃興期)を丹念に追ってはいるのだが、100ページも写真に使っているので、分量が少なく物足りない感じもする。著者がまえがきで述べているように、著者自身が実際にそのシーンの中で体験したことのみがベースとなっているので、仕方がないのか・・・。
しかし、この本でしか見れないようなライブのちらしなどの多くの図版類は貴重だ。今みたいにパソコンで手軽に作れるものではないので、バンドやイベントの特徴が表れていて眺めているだけで楽しい。ちらしも100ページくらい欲しいくらいだ。
2011年05月23日
新緑の釣行

日曜は全国的に雨の予報が出ていたのですが、天気予報をチェックして午前中は天気が持つハズと福井県へ遠征しました。
土曜の夜に京都を出たときは、まだ星明かりも見えていた空が、現地で5時30分に目覚めたときにはどんよりと曇っていて、与えられた時間が少ないことを示唆していました。しかし、雨の予報のおかげか、いつもの釣り人が右往左往している人気河川に先行者はなく、6時前には竿を出しました。
しばらく当たりがなかったのですが、7時をまわって少し気温があがったのでしょうか、小さなカワゲラが飛んでいるのが見えるようになりました。そしてTさんが25センチと28センチのイワナを続けてヒット。
僕も集中して流れに向かいました。
しかし、パラダン、ソラックス、CDCと焦ってフライを変えても僕のフライには、一度もイワナが出ることはなく、9時過ぎには雨が降り始めました。

新しい緑が、ぐいぐいと芽を伸ばしている大きな木の下で雨が小降りになるのを待っていたのですが、雨が激しくなるばかりで、10時前には車に戻りました。冷たい雨が身に沁みます。用事もあったので、竿を片付け、帰路につきました。
GW釣行に続き、またしてもボウズです。つぎの釣行は6月の予定。次ぎもボウズだとちょっとやばいです・・・。
タグ :イワナフライ・フィッシング
2011年05月20日
京都みなみ会館5–6月号

今年度も会員の更新をしたので、みなみ会館から5月〜6月の上映スケジュールがはいったリーフレットが届きました。
今月、まずチェックしたいのは『ドクター・フィルグッド』です。ドクター・フィールグッドのCDは一枚も持っていないのですが、ピストルズ、クラッシュの映画を撮ったジュリアン・テンプルの作品です。みなみ会館で上映されるロック映画にハズレはありません。27日までの上映なので、急がないと・・・。
あとはペルーの映画『悲しみのミルク』はぜひ見たいと思っています。
ところで、みなみ会館のホームページを開いたら、アルバイトスタッフを募集していました。週3日以上ならなんとかなるかも知れないのですが、フリーター優先なので、厳しいかも・・・。5月22日迄に書類を郵送しないといけません。まだぎりぎり持参すれば間に合います!
■京都みなみ会館HP
2011年05月14日
空豆のパスタ

今年も実家からたくさんの空豆が送られてきたので、さっそく塩茹でし食べました。いつもは皮付きのままパスタにいれるのですが、今日はパスタを茹でている間に、熱々の皮を剥いてから、パスタに絡めました。豆の甘みが増してちょっと贅沢な味になりました。
もちろん皮付きの空豆も苦みがあってビールとの相性がバツグンです。まさに初夏の味が口いっぱいにひろがります。
タグ :空豆
2011年05月13日
『悪魔物語・運命の卵/ブルガーコフ』
『悪魔物語・運命の卵/ブルガーコフ (岩波文庫)』を読了。
ロシア文学といえば、皆なコートの襟をたて毛糸の帽子を被り難しい顔をして街路を歩いてるようなイメージがあります。それは聞き慣れないコロトコフやエヴグラフォヴナ、イパーチエヴィッチ・ペルシコフという名前をすらすらと読めないために、自分の眉間にも皺が寄って余計難しい顔になるのですが、ブルガーコフのこの2つの中編は名前のハードルさえ超えれば大丈夫。すらすら読めます。
特に「運命の卵」の後半は巨大化した蛇が暴れだし、B級ハリウッド映画的(もしくはハリウッド以外のパニック映画的)で、ロシア文学の小難しいイメージを一掃してくれます。
なにより「運命の卵」は革命後間もない1920年代にソヴィエトで書かれた中編SFなのに、現在の日本とあまりにリンクしているところが多くて、ストーリーよりもそっちの方が怖くなります。生命を活性化させる赤色光線はまさしく放射線だし、鶏が次々に死んでいく疫病は鳥インフルエンザや口蹄疫、供給の減った鶏(と卵)を赤色光線で増やしてひともうけをたくらむような人物は古今東西引きも切らず、些細なミスや意図的な手抜きによって大きなダメージを被ります。
読後に岩波文庫の表紙の写真を見ると、煙草をくわえたブルガーコフの黒い影の部分が、「ウルトラQ」のように渦をまきながら広がってきました。ブルガーコフの長編『巨匠とマルガリータ』が、池澤夏樹が編集した世界文学全集にラインナップされています。