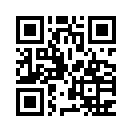2011年03月19日
『釣山河/山本素石』
『釣山河/山本素石』(二見書房)を読了。
昭和50年に発刊されたこの本は山本素石が昭和40年代に釣り雑誌『釣の友』に連載したエッセイをまとめたものだ。少年時代の釣のまつわる思い出から戦後紀伊半島の川を巡る絵描きの行商時代(この頃の話しは『つりかげ』に詳しい)や佐渡島への釣旅行などが綴られているなかで、滋賀県の愛知川上流にあたる茶屋川の奥にあった茨川という廃村にまつわるいくつかの回が印象的だ。
フライフィッシングをはじめてすぐの頃、茶屋川へはよく通った。当時、仕事で付き合いのあったひとから同じ愛知川の支流である御池川では昔、魚が湧くほど泳いでいたと聞いていたし、源流へ行けば魚が居るという考えにとりつかれていたので、集落のない茶屋川は源流の名に相応しい川だと思っていた。しかし林道が川沿い通り、車で奥まで詰めることができるその川で印象に残る釣りをした覚えはない。たまに釣れるアマゴは20センチに満たないものだったし、全体に流れは細く、水量も少なくてアブラハヤの方がよく釣れ、その度に舌打ちをし、やがて足も運ばなくなった。
『釣山河』にも記されている茨川へ向かう途中にあるトンネルのことは覚えている。そのトンネルの前後からよく入渓したはずだが、その当時、茨川の廃村跡まで釣りあがっていたか、どうかはよく覚えていない。建物や廃屋の跡を見た覚えはないので、そこまで行ったことはなかったのかも知れない。
山本素石は、打ち捨てられてまもない民家にあがりこんで、仲間と、あるいはひとりで静かな夜を過ごす。夜の闇の中で囲炉裏に火をくべながら、日本の高度成長のなかで棄てられるしかなかった朴訥な山の生活のことを考えるのだ。
以前から知己のあった人物がその茨川の小さな集落の出身であることが明かされるくだりには、山本素石同様にびっくりした。そういう不思議な縁が描かれている中では、山本素石が少年の頃、彼の叔父が狐をだましだまされる話しも、そのディテールの詳しさによって本当の話としか思えなくなる。山村ではかってひとを騙し、化かす狐が存在したのだ・・・。そしてそれは山本素石が追い求めたツチノコの存在にも信憑性を与えるのだ。