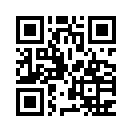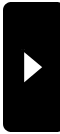2009年05月18日
忙しすぎたから

フォーク時代のRCサクセション。セカンドの『楽しい夕べに』におさめられた曲はどれも名曲だ。特に破廉ケンチがメインボーカルをとる「忙しすぎたから」が好きだ。
作詞はリンコさんなのだが、破廉ケンチの声も悪くない。なにより曲の後半にバック・ボーカルではいる清志郎の声が僕はたまらなく好きだ。
“このごろはいつもだれも口をきいてきいてくれないから
ぼくはさみしくて気が狂いそう”
清志郎の声と、その声で歌われる歌詞とメロディもいい。絶妙のバランスで清志郎は切なさと狂気を孕んだ歌を歌うのだ。
清志郎の声はチャボの声ともよくはまる。『ティアーズ・オブ・クラウン』で演奏される「打破」で後半、チャボに呼び出される形で歌いだす清志郎のパートも背筋に電気が走って僕のバッテリーはビンビンになる。
「忙しすぎたから」が収録されている頃のライブを見たい。何年か前にロック画報という雑誌でRCサクセションの特集があったときに70年代初期の未発表ライブが6曲納められたCDが付いていた。
1.つまらない仕事(未発表曲)
2.ぼくとあの娘
3.忙しすぎたから
4.内気な性格(未発表曲)
5.もっと何とかならないの(未発表曲)
6.ぼくの自転車のうしろに乗りなよ
それはお宝の名に相応しい貴重でスリリングな演奏だった。もしかするとこの5年くらいの間で最も聴いたRCのCDかも知れないくらいよく聴いた。6曲といわず、ライブ全部を通した音源はリリースされないのか(この6曲のマスタリングを清志郎と破廉ケンチが担当していたのが不思議だったのだが・・・。なぜリンコさんではなく・・・。)?
不謹慎だけど、このタイミングにリリースしてくれないのかな?
2009年05月16日
ヒッピーに捧ぐ
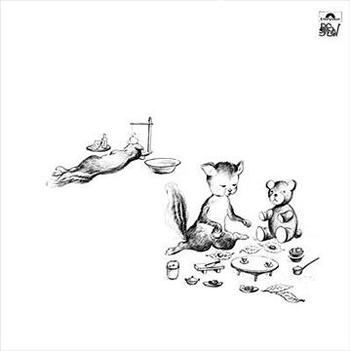
『シングル・マン/RCサクセション』
みなみ会館の映画上映を主催するRCSの会報が届いた。会報に忌野清志郎の死に関するコメントがはいっているのだがRCSの名前がRCサクセションに由来していると書いてあった。
RCSのひとも清志郎の歌に後押しされて、ずっと頑張ってきたのだ。
そういえば清志郎の描く歌詞はすごく映像を喚起させるものがある。わずか4~5分のポップ・ミュージックが2時間の長編映画のようにストーリーを感じさせる。
市営グランド駐車場に停めた車のなかの恋人同士が過ごした一夜の思い出を歌う「スローバラード」。悪い予感のかけらもないさ(不安に押しつぶされそうなのを抗っているようにも聴こえる)と、情感たっぷりに歌われる。
バンドマンとの恋の逃避行は「ラプソディ」。音楽が好きな高校生の日常を歌う「トランジスタ・ラジオ」。すべての労働者に捧ぐ格差社会先取りソングの「いいことばかりはありゃしない」。僕と彼女と友人お日隅くんのことを「去年の今頃」、「日隅くんの自転車のうしろに乗りなよ」、「ぼくの自転車のうしろに乗りなよ」の三つの歌もなかなかだ。
他にもたくさんたくさんあるのだけど、映画にしたいRCソングナンバー1ははやはり「ヒッピーに捧ぐ」だ。
いつもと同じ朝。かわらない日常。だけど友だちは死んでしまってもういない。それでも続くコンサート。死を受けとめるバンドマンとコンサートの対比が見事だ。ほんとに誰か映画にしないかな。主演は今なら断然、松山ケンイチだ。で死んでしまうのは峯田だ(逆でも可)。
RCの歌の映画化はともかく初期のRCサクセションから復活ライブまでを網羅するようなドキュメンタリー映画はいつかきっと作られるだろう。ジョー・ストラマーの『VIVA JOE STRUMMER』やイアン・カーティスを追った『JOY DIVISION ジョイ・ディヴィジョン』のように。ディランの『ノー・ディレクション・ホーム』のように(続編はいつ?)。
そんな映画、今観たら泣いてしまいそうだけど・・・。
そういえば僕は未見なのだが、ラフィータフィー時代のライブを追ったドキュメント映画『不確かなメロディー』があったはずだ。今度レンタル屋さんで探してみよう。みなみ会館で追悼上映はしないかな?
2009年05月12日
トランジスタ・ラジオ

『PLEASE / RCサクセション』
はじめて清志郎をみたのは坂本龍一とやった「いけないルージュ・マジック」だった。そのあとベストテンで「サマーツアー」がランクインしているのをみたのだけど、小学生だったので、どっちかっつーと怖かった。
中学3年生の頃から洋楽を聴くようになって、日本のロックにも興味をもつようになり再びRCサクセションにまみえることになる。で、それから高校時代を通じていちばん馴染みの深かったナンバーが「トランジスタ・ラジオ」だ。
とにかく地方都市ですらない何もない田舎町にレンタルレコード店はあったものの、ちゃんとしたレコードプレーヤーを持っていなかった僕はラジカセだけが音楽に触れることができるかけがえのない機械で、週間FM(当時はFMの番組表と音楽情報メインのFM誌が数誌出ていた。週間FMには清志郎が『忌野旅日記』を連載していた。今でもかわりのないタッチの絵が文章に添えてあった)で曲目を確認しつつ、とにかくいろんな曲をエア・チェックしていた(もちろんベスト・ヒットUSAとMTV、ポッパーズMTVは見逃さなかった。でもうちにはビデオがなかった・・・)。
「サウンド・ストリート」と「クロス・オーバー・イレブン」。そして平日の夕方に小嶋さちほがDJをしていた番組とか、地方局のリクエスト番組(RCの曲で“ベイビー”と云わない曲として「不思議」がかかったのを覚えてる)があって、カセットテープに録音して気に入った曲をダビングしていた(ダブルカセットだったのだ!)。
その頃の香川に民放のFM局はなくて、やたらクラシックばかりかけているNHK-FMだけが僕の音源だったのだが、もしかするとその頃がいちばん自由にいろんな音楽に触れていたかも知れない。
「トランジスタ・ラジオ」のように屋上での甘い思い出はないのだが、ベイエリアや リバプールから届くナンバーに僕は耳をすまし、ちっとも開かれているように思えない未来に不安になったりした。でもそんなときも清志郎の声はいつもポジティブで僕にもなにかが起こせそうな気がしたのだ。
2009年05月11日
バンドマン、歌ってよ。
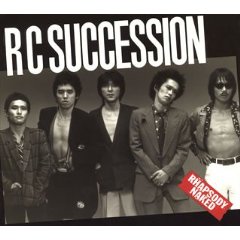
『RHAPSODY / RCサクセション』
バンドマンとしての清志郎が好きだった。
そして僕にとって清志郎=RCサクセションであり、決してRCサクセション=清志郎ではなかったので、清志郎の新しいバンドにはピンとこないまま10年が過ぎ、さらにこの10年はCDすら持っていない始末だ。20年前のRCの解散をぐずぐずと引きずっている悪いファンのひとりだった。
“バンドマン、歌ってよ”と歌われる「ラプソディー」が収録されている久保講堂のライブ盤はRCのライブ盤の中でも特別だ。なにしろRCの黄金期を支えたメンバーでの「よォーこそ」が収録されている。バンドのメンバーを順番に紹介していきながらライブはいきなり最高潮を迎える。メンバー紹介を歌にして、しかもメンバー全員が最高だぜ、ごキゲンだぜと自画自賛しながらシャウトする忌野清志郎は素敵すぎる。
新井田耕造とGee2woが抜け、『Baby a Go Go』のリリースされた後、RCは活動停止になるのだけれども、すぐに活動を再開すると思っていた。ところが1994年になって清志郎とチャボの『GLAD ALL OVER』がリリースされた。RCの曲を清志郎とチャボで目いっぱい演奏している。そこにはリンコさんの姿すらなく、RCの解散を決定事項になったのだと思うしかなかった。そのときも大きな喪失感があった。
その『GLAD ALL OVER』でも「よォーこそ」が演奏されている。サポートメンバーの中には大好きなKYONもいたのだが、なんだか腑抜けたテンションで何回聴いても僕は盛り上がれなかった。あれこそバンドのマジックだったのだ。清志郎だけでなく、チャボが居て、リンコさんが居て、新井田耕造が居て、Gee2woが居て、梅津さんも居て、それでメンバー間で大きな化学反応が起こっていたのだ。その化学反応こそがロックンロールなのだ。
週末もずっとRCのアルバムばかり聴いてました。僕の追悼はまだ終わっていません。
2009年05月09日
僕たちには忌野清志郎がいた
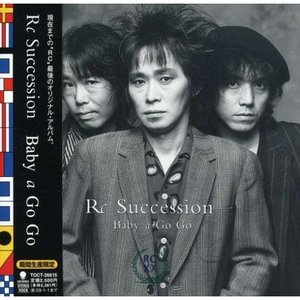
『Baby a Go Go / RCサクセション』
かってアントニオ猪木と藤波辰巳の試合で古館伊知郎は「ビートルズはお兄ちゃんのものだった。 安保には間に合わなかった。僕たちには何もなかった。 しかし、アントニオ猪木がいた」と実況した。
僕が音楽を聴き始めた80年代前半には「ビートルズはもうなかった。ストーンズは決して来日できなかった。ボブ・ディランはよくわからなかった。クラッシュやピストルズには間に合わなかった。僕たちには何もなかった。しかし、忌野清志郎がいた」のだ。
忌野清志郎は少年のようなシャイネスと童貞のようなナイーブさをもっていた。同時に大人のしたたかさとずるがしこさも持っていた。さらに幼児のように残酷でもあった。そしてそれらを全部ユーモアで包むこともできた。
ロックの神というよりは悪魔なんだけど、天使のようにイノセントな笑顔で笑うことがあった。世間のしがらみや重力から徹底的に自由でありながら、社会的な存在でもあった。
あの声とあの歌で、大きな愛で包みこみながら、おまえ自身はどうなのだと鋭く追及した。
かって世界は単純で「RCを聞いているか?清志郎が好きか?」でいろいろなことを判断することができた。仲間と敵を見分けるのは簡単だった。
「大人だろ 勇気をもてよ」と清志郎は歌ったのだが、僕は勇気を持っているのだろうか。