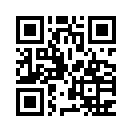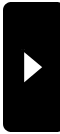2007年05月24日
電飾看板
I got my name in lights with notcelebrity.co.uk
電飾看板をつくってみました。
「Name in Lights」というサイトで作れます。
看板の後ろの光線が清水寺の夜間拝観時に京の夜空を切り裂くビーム光線に似ています。
2007年05月24日
日曜日の釣り
20日の日曜日には福井まで日帰り釣行。
九頭竜川のその支流へ行くのは2年ぶり。朝9時に京都を出発。湖西から福井にはいるまで、ずっと時雨れて、北陸道の南条SAで休憩してたときの気温は10度を下回り、アイスクリームのサンプリングをしているのが寒々しく見えました。
目的の川に着いたのは午後1時頃で、ときおり青空が広がるまで回復。日がさすと、さすがに気温があがり、天候のせいか日曜にしては釣り人も少ない感じです。
7時頃まで釣って20〜25センチのイワナが5匹。まずまずの釣果です。いつものことですが、フックしたにもかかわらず逃した魚は、もう少し大きかったように思えました。
同行のTさんの釣果も同じくらいでした。

九頭竜川のその支流へ行くのは2年ぶり。朝9時に京都を出発。湖西から福井にはいるまで、ずっと時雨れて、北陸道の南条SAで休憩してたときの気温は10度を下回り、アイスクリームのサンプリングをしているのが寒々しく見えました。
目的の川に着いたのは午後1時頃で、ときおり青空が広がるまで回復。日がさすと、さすがに気温があがり、天候のせいか日曜にしては釣り人も少ない感じです。
7時頃まで釣って20〜25センチのイワナが5匹。まずまずの釣果です。いつものことですが、フックしたにもかかわらず逃した魚は、もう少し大きかったように思えました。
同行のTさんの釣果も同じくらいでした。
2007年05月23日
鴨川の花粉
マンガミュージアムの帰り、鴨川の河川敷を電動付自転車で走っていると、途端に目が痒くて痒くてしようがなくなりました。川沿いに繁茂する雑草のなにかが強烈な花粉を放っているに違いありません。よくきくのはブタクサですが、ネットで調べるとブタクサの花粉は夏から秋に飛散するそうなので、また別の雑草みたいです。
そう長い距離を走ったわけではなく、時間にして10分もかかっていないはずなのに、かなり強い痒みが脳みそを刺激しはじめたので、逃げるように鴨川から離れました。
痒い話といえば、内田百閒の「掻痒記」です。読んでいるうちに誰もが持っている痒みの記憶が呼び起こされ、痒くもないのに、身体中がむずむずしてしようがありません。
とにかく、今の季節、鴨川に近づくのは注意が必要だということです。
2007年05月22日
海洋堂フィギュアミュージアム展
息子を連れて国際マンガミュージアムの「海洋堂フィギュアミュージアム展」を見てきました。

海洋堂といえば、食玩のフィギュアで有名なのですが、ガンプラ第一世代の僕にはガレージキットの海洋堂のイメージが燦然と輝いていて、現在のような一般にも認知されるような大ブレイクは奇跡のような話です。造形を突き詰めた結果、コアなユーザーの集うマニアックな世界から突き抜けて、広く世間に受け入れられるようになった、まったくマンガみたいなサクセスストーリーが痛快です。
で、フィギアミュージアム展は基本、食玩の展示でした。もちろん優れた造形の食玩が無数に並んでいるのは見ていて楽しいのですが、僕としては、もっと海洋堂の一点ものの大きなフィギュアとか、ジオラマ模型とかを期待していたので、ちょっと拍子抜けでした。どこにもそんな告知が出ていないですし、僕の勘違いですが、これでは中国の食玩製造工場の製品展示ではないかと、悶々とした気持ちになりました(ちょい辛口です!)。
「恐竜を見にいこう」と誘った息子は僕とは違い、恐竜の食玩をはじめとした動物や昆虫のフィギュアに夢中でした。(展示会場自体はそう広くないので)会場内を何度もぐるぐるとまわっていました。
展示会の景品として無地のフィギュアをもらい、彩色するコーナーがありました。ティラノザウルスのが欲しかったのですが、見事に外れ息子が手にしたのはドン・キホーテです(彩色されたドラゴンももらいました)。なぜ、ドン・キホーテなのかは知りませんし、息子にこれは何かと訊かれても「ドン・キホーテだ」としか答えることができないのですが、意外に楽しげに色を塗り始めました(すぐに飽きてしまいましたが・・・)。

マンガミュージアムへ行くのは2度目だったのですが、ゆっくり時間を過ごしたのは初めてでした。息子と紙芝居を見たり、絵本コーナーで絵本を読んでやったり、まるでよい父親のように振る舞いまった土曜日の一日でした。もちろん、マンガもまとめて読みましたよ。
■国際マンガミュージアムHP
海洋堂といえば、食玩のフィギュアで有名なのですが、ガンプラ第一世代の僕にはガレージキットの海洋堂のイメージが燦然と輝いていて、現在のような一般にも認知されるような大ブレイクは奇跡のような話です。造形を突き詰めた結果、コアなユーザーの集うマニアックな世界から突き抜けて、広く世間に受け入れられるようになった、まったくマンガみたいなサクセスストーリーが痛快です。
で、フィギアミュージアム展は基本、食玩の展示でした。もちろん優れた造形の食玩が無数に並んでいるのは見ていて楽しいのですが、僕としては、もっと海洋堂の一点ものの大きなフィギュアとか、ジオラマ模型とかを期待していたので、ちょっと拍子抜けでした。どこにもそんな告知が出ていないですし、僕の勘違いですが、これでは中国の食玩製造工場の製品展示ではないかと、悶々とした気持ちになりました(ちょい辛口です!)。
「恐竜を見にいこう」と誘った息子は僕とは違い、恐竜の食玩をはじめとした動物や昆虫のフィギュアに夢中でした。(展示会場自体はそう広くないので)会場内を何度もぐるぐるとまわっていました。
展示会の景品として無地のフィギュアをもらい、彩色するコーナーがありました。ティラノザウルスのが欲しかったのですが、見事に外れ息子が手にしたのはドン・キホーテです(彩色されたドラゴンももらいました)。なぜ、ドン・キホーテなのかは知りませんし、息子にこれは何かと訊かれても「ドン・キホーテだ」としか答えることができないのですが、意外に楽しげに色を塗り始めました(すぐに飽きてしまいましたが・・・)。
マンガミュージアムへ行くのは2度目だったのですが、ゆっくり時間を過ごしたのは初めてでした。息子と紙芝居を見たり、絵本コーナーで絵本を読んでやったり、まるでよい父親のように振る舞いまった土曜日の一日でした。もちろん、マンガもまとめて読みましたよ。
■国際マンガミュージアムHP
2007年05月19日
浄瑠璃寺の吉祥天女像と「見仏記」
浄瑠璃寺の吉祥天女像の春の公開が今週末の5月20日までということが、今日事務所で流れているFMラジオでアナウンスされていました。
一応、秘仏なんだけど、浄瑠璃寺の吉祥天女像は年に3回、それも正月元日〜15日、春3月21日〜5月20日、秋10月1日〜11月30日と、わりに気前よく開帳されてます。清水寺の33年に一度開帳される千手観音立像とは同じ秘仏でもその㊙ぶりが全く違います(※清水寺奥の院の本尊である千手観音坐像は2003年に開帳されたのが243年ぶりという、まさにキング・オブ・秘仏のような存在です。243年前といえば、1760年/宝暦10年、葛飾北斎が誕生した年です)。
木津川の南、山城の国とよばれていた静かな里山にある浄瑠璃寺に僕は行ったことがありません。
みうらじゅんといとうせいこうの「見仏記」が出た1993年9月の(単行本持ってる)、たぶんその少し前に、近くの岩船寺までは行ったことがあるのですが・・・。当時の僕は岩船寺という古代の飛行機(宇宙船?)のような名前のお寺に興味は持っていても、浄瑠璃時はまったく視野にはいっていませんでした。

「見仏記」には吉祥天女像から溢れるフェロモンの虜になっているみうらじゅんの妄想が描かれています。お寺を巡る“観光”とは違う“見仏”という行為に僕はおおいに共感し影響を受けました。単純にみうらじゅんの仏像に対する深い愛と、いとうせいこうのみうらじゅんに対する深い愛がおもしろかったのですが・・・。
しかし、残念ながらみうらじゅんの暴走する妄想を、ときには笑いとばし、ときには優しくフォローするいとうせいこうのような相棒が僕にはいませんでした・・・。
近くのTSUTAYAに「TV見仏記」シリーズの中古DVDが売っていて、欲しくてしようがありません。でも1枚2000円で5巻くらい揃っているので1万円かと思うと僕のこづかいでは買えません・・・。
■浄瑠璃寺 Wikipedia
一応、秘仏なんだけど、浄瑠璃寺の吉祥天女像は年に3回、それも正月元日〜15日、春3月21日〜5月20日、秋10月1日〜11月30日と、わりに気前よく開帳されてます。清水寺の33年に一度開帳される千手観音立像とは同じ秘仏でもその㊙ぶりが全く違います(※清水寺奥の院の本尊である千手観音坐像は2003年に開帳されたのが243年ぶりという、まさにキング・オブ・秘仏のような存在です。243年前といえば、1760年/宝暦10年、葛飾北斎が誕生した年です)。
木津川の南、山城の国とよばれていた静かな里山にある浄瑠璃寺に僕は行ったことがありません。
みうらじゅんといとうせいこうの「見仏記」が出た1993年9月の(単行本持ってる)、たぶんその少し前に、近くの岩船寺までは行ったことがあるのですが・・・。当時の僕は岩船寺という古代の飛行機(宇宙船?)のような名前のお寺に興味は持っていても、浄瑠璃時はまったく視野にはいっていませんでした。
「見仏記」には吉祥天女像から溢れるフェロモンの虜になっているみうらじゅんの妄想が描かれています。お寺を巡る“観光”とは違う“見仏”という行為に僕はおおいに共感し影響を受けました。単純にみうらじゅんの仏像に対する深い愛と、いとうせいこうのみうらじゅんに対する深い愛がおもしろかったのですが・・・。
しかし、残念ながらみうらじゅんの暴走する妄想を、ときには笑いとばし、ときには優しくフォローするいとうせいこうのような相棒が僕にはいませんでした・・・。
近くのTSUTAYAに「TV見仏記」シリーズの中古DVDが売っていて、欲しくてしようがありません。でも1枚2000円で5巻くらい揃っているので1万円かと思うと僕のこづかいでは買えません・・・。
■浄瑠璃寺 Wikipedia
2007年05月15日
川の思いで

GWは飛騨地方でなかなかよい釣りができました(もう1週間も前だけど)。
もうフライを始めて10年以上になるけれど、岐阜県の川は苦手でした。あんまり釣れた記憶がありません。あんなにきれいな川がたくさんあるのに、どの川も僕にはひどくつれなかったです。 それが、今回の釣行では、サイズはものたりなかったのですが、コンスタントにイワナが釣れたのでした。こんなの初めてです。
だいたい岐阜県の川はどこも釣り人が多過ぎるのです。
あぁ、この辺よさそうだなぁと思って川沿いに移動していると、車が止まり(たいてい尾張小牧ナンバーだったりします!)、川の中に先行者がたっています。たぶん、僕がフライを始めた頃は今よりも釣りブームで特に釣り人が多かったようです。その当時は日本の人口が半分になればいいのにと本気で思っていました。
もちろん、釣り人が多いだけが釣れない理由ではなかったのですが、そんな釣果のあがらない川に僕は何度も通ったのでした。
フライを始める前に一度、僕は長良川の支流、吉田川で泳いだことがあります。ひどく暑い夏の日のことでした。当時はまだ東海北陸自動車道ができる前で長良川に沿ったぐねぐねと曲がりくねった長い道のりを走って郡上八幡に着いたのでした。
吉田川の清流は夏の日射しを浴びてきらきらと輝いてました。外はうだるような夏の暑さなのに、川の水はおそろしく冷たくて数分も入っていられませんでした。ちょっとした淵には大きな鮎と無数の小さなアマゴが群れて泳いでいました。
それは長良川河口堰のできる前の最期の清流の最期の時期だったのかも知れません。手を伸ばせば触れられそうなほどのアマゴや鮎が目の前を泳いでいるのです。で、手を伸ばすと、やっぱりすいすいと軽く逃げられました。宝石のように輝く魚たちに圧倒され、子どもみたいにはしゃいだのでした。
フライをするようになって、初めての遠征で訪れたのはやっぱり吉田川だったのですが、まったく釣れませんでした。その川の豊かな魚の光景が記憶に鮮明に残っていただけに、釣れない事実はまったく受け入れがたいものでした。まだ春先だったのに、潜って魚が居ることを確認したくてしようがありませんでした。
何年たっても釣りはうまくならないけれど、ときどき何かの拍子で、よい釣りをすることができて、その記憶を頼りにまた川へ向います。釣れなくても、やっぱり悔しくて、釣れた記憶といっしょにあの夏の吉田川をたぐり寄せて、また次ぎの釣行を計画します。
えっと、今度は6月かなぁ。7月には富山にも行きたいですね。