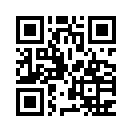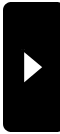2007年06月28日
賀茂大橋のオナガサナエ
賀茂大橋の欄干の上でトンボを発見!オニヤンマにしては体長が6〜7センチ位でちょっとこぶり。オニヤンマにしかない作り物じみた存在感が希薄なので、ネットで調べてみるとどうやらオナガサナエというトンボらしい。オスの尾の先が長いのが特徴的。↓
きっと逃げてしまうんだろうと思いながら、そっと近づいても飛び立つ気配がありませんでした。翡翠色をした大きな眼のうしろに筋肉の固まりのような胸部が膨らんでいます。薄い羽根の幾何学的な紋様が恰好いいです。
2007年06月17日
瓜生山の毛虫
虫取りに行きたいというので、瓜生山へはいったのですが、息子が考えていたようなクワガタやカブトムシは見つからず、1時間もしないうちに疲れたもう帰るという始末です。
帰り際に小さな沢の近くで見つけたのはマイマイガの幼虫。対になった赤と青の斑点が特徴的です。
2007年06月10日
疎水のホタル
この辺りで有名なホタルスポットといえば、哲学の道なのですが、今年は疎水の広範囲にホタルがひろがっているようです。伊織町の方ではホタルを放流したという話をききました。
昨夜、近所の疎水を歩くとちらちらと明滅を繰り返すホタルを結構見つけることができました。哲学の道に比べるとずっと人通りも少なく、ときおり犬を連れているひとが感嘆の声をあげるくらいでした。
でも、交通量の多い大通りも近く街灯も明るいので、静かにホタルを鑑賞するにはちょっと場違いな感じです。

僕の田舎では、僕がものごころついた頃に、田んぼ沿いに張り巡らせられた用水路がすっかりコンクリートで塗り固められてしまい、ホタルは完全に姿を消してしまいました。幼い頃、つかまえたホタルを小さな虫かごに入れて、枕元の置いて寝たことを微かに思い出すことができるのですが、小さな虫たちが豊かに暮らす用水路は失われ、中途半端な都市化が田舎の光景を無惨なものに変えていったのです(今、その用水路にはジャンボタニシが繁殖し、夏になるとアメリカのお菓子のようなショッキングピンクの卵を水路側面に産みつけ、僕の頭をくらくらさせます)。
会社の先輩にきくと、鴨川も昔に比べずっときれいになったとききます。ホタルが生息できるような環境がすこしづつ取り戻されているのは、きっといいことなのでしょうが、ホタルをばらまくような環境保全には、むしろもやもやとした違和感を感じずにいられません。
息子はホタルを見つけると、興奮して大きな声で教えてくれました。素直なココロでホタルを楽しんでいます。ホタルのお尻がどうして光るのかうまく説明できなかったので、このあと勉強しておきます・・・。
昨夜、近所の疎水を歩くとちらちらと明滅を繰り返すホタルを結構見つけることができました。哲学の道に比べるとずっと人通りも少なく、ときおり犬を連れているひとが感嘆の声をあげるくらいでした。
でも、交通量の多い大通りも近く街灯も明るいので、静かにホタルを鑑賞するにはちょっと場違いな感じです。
僕の田舎では、僕がものごころついた頃に、田んぼ沿いに張り巡らせられた用水路がすっかりコンクリートで塗り固められてしまい、ホタルは完全に姿を消してしまいました。幼い頃、つかまえたホタルを小さな虫かごに入れて、枕元の置いて寝たことを微かに思い出すことができるのですが、小さな虫たちが豊かに暮らす用水路は失われ、中途半端な都市化が田舎の光景を無惨なものに変えていったのです(今、その用水路にはジャンボタニシが繁殖し、夏になるとアメリカのお菓子のようなショッキングピンクの卵を水路側面に産みつけ、僕の頭をくらくらさせます)。
会社の先輩にきくと、鴨川も昔に比べずっときれいになったとききます。ホタルが生息できるような環境がすこしづつ取り戻されているのは、きっといいことなのでしょうが、ホタルをばらまくような環境保全には、むしろもやもやとした違和感を感じずにいられません。
息子はホタルを見つけると、興奮して大きな声で教えてくれました。素直なココロでホタルを楽しんでいます。ホタルのお尻がどうして光るのかうまく説明できなかったので、このあと勉強しておきます・・・。
2007年06月04日
ムネアカオオアリの巣立ち
北陸の山中でムネアカオオアリの巣立ちを発見。背の高い杉の木の根元がうろのようになっていて、そこから這い出した無数の羽アリが杉の木を登っていきました。
普通でもかなり大型のムネアカオオアリですが、メスの羽アリは体長が2センチ位あって、琥珀色をした胸が艶々としていています。
オスの羽アリと、羽のないアリもわさわさと群がっていてかなり不気味です。
2007年03月12日
冬を越すクビキリギリス
修学院の奥さんの実家で見つけたクビキリギリス(たぶん)。屋上で遊んでいると息子が見つけました。まだ冬眠中のところを無理矢理撮影。息子が触ろうとすると、足をばたばたさせて、いやがります。その度に「わぁあ〜」とか、「きゃぁあ」とかうるさくてしようがありません。
口の大あごの部分が鮮やかなオレンジ色をしています。触覚もかなり長いのが特徴。今日は雪もちらちらと降るような寒い日だったので、動きも鈍く、じっと寒さに耐えているようでした。
子どもの頃、バッタの類を捕まえると、口から茶色い汁を出すのがどうにも苦手でした。
【追記】クビキリギリスではなくクビキリギスという名前だということが判明しました。キリギリスの仲間なのにわざわざキリギスとする理由が知りたいです。誰か教えてください。
2007年01月05日
冬休み日記
実家に帰っていた間は息子のためにじーちゃん、ばーちゃんがいろいろもてなしてくれた。 元旦にはニューレオマワールドの一角にある「せとうち夢虫館」へ行ったのだが、想像していたものよりずっと楽しめたのだ。

入館するとすぐにやんばるの森という温室があって、そこにオオゴマダラという蝶が放し飼いにされてあって、虫ゴコロがくすぐられた。ヒラヒラとキレイな蝶が舞っているのを観ると、それだけで癒されます。

その隣にかぶと・くわがたファームがあって、そこにはアトラスオオカブトとヒラタクワガタが居る。こっちは狭くてカブトも傷んでいる。たぶん大きくして数を増やすとこっそり持って帰る人が居るのだと思う(広い館内にスタッフはまばらだ)。でも実際に間近で観ることができる大きなカブトムシに息子は大喜び。
※HPをみると将来的には自然繁殖させたカブトムシやクワガタを自由に持ち帰れるようにするようです!←これは楽しい!しかし虫取りの喜びは自然の方がずっと大きいっす。
あとは映像と昆虫標本の展示がメインなのだが、旧レオマの建物を再利用しているので、スペースの取り方がちょっと不自然。昆虫写真で有名な海野和男の迫力のある写真があったり、携帯で動画を観れるようにもなってます。
思いがけずおもしろかったのが「森の虫松」先生の虫クイズ。実際に珍しいクワガタに触れながら子どもがクイズに答えるのだけど、先生の司会ぶりがうけます。
図書館の本もいろいろあって子どもより大人の方が夢中になれます。でも入館料大人1500円はちょい高め。地元なら年間パスポート3000円(だったと思う)にした方がよさそう。
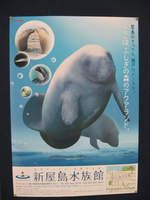 ところでこの夢虫館は新装開店となった屋島水族館と同じ日プラの子会社が運営している。夏にいったときにずいぶんさびれた印象が強かった屋島水族館は知らない間にいったん閉館になっていた。事業を引き継いだのが水族館業界で有名な(ブルータスの水族館特集にも載っていた)日プラ。ここのアクリルパネルの技術は世界一らしく大阪の海遊館や沖縄美ら海水族館をはじめ、海外の水族館の大型水槽を製作している。その原点が屋島水族館の水槽で、その縁から事業を引き継いだそうだ。
ところでこの夢虫館は新装開店となった屋島水族館と同じ日プラの子会社が運営している。夏にいったときにずいぶんさびれた印象が強かった屋島水族館は知らない間にいったん閉館になっていた。事業を引き継いだのが水族館業界で有名な(ブルータスの水族館特集にも載っていた)日プラ。ここのアクリルパネルの技術は世界一らしく大阪の海遊館や沖縄美ら海水族館をはじめ、海外の水族館の大型水槽を製作している。その原点が屋島水族館の水槽で、その縁から事業を引き継いだそうだ。
地元に水族館がないというのは(動物園もつぶれて久しいし)寂しいことなので、日プラさんに感謝。それだけで夢虫館も応援したくなります。旧屋島水族館から流れてきたイトウの剥製は余計だけど・・・。

■せとうち夢虫館HP
■新屋島水族館HP
■日プラHP
入館するとすぐにやんばるの森という温室があって、そこにオオゴマダラという蝶が放し飼いにされてあって、虫ゴコロがくすぐられた。ヒラヒラとキレイな蝶が舞っているのを観ると、それだけで癒されます。
その隣にかぶと・くわがたファームがあって、そこにはアトラスオオカブトとヒラタクワガタが居る。こっちは狭くてカブトも傷んでいる。たぶん大きくして数を増やすとこっそり持って帰る人が居るのだと思う(広い館内にスタッフはまばらだ)。でも実際に間近で観ることができる大きなカブトムシに息子は大喜び。
※HPをみると将来的には自然繁殖させたカブトムシやクワガタを自由に持ち帰れるようにするようです!←これは楽しい!しかし虫取りの喜びは自然の方がずっと大きいっす。
あとは映像と昆虫標本の展示がメインなのだが、旧レオマの建物を再利用しているので、スペースの取り方がちょっと不自然。昆虫写真で有名な海野和男の迫力のある写真があったり、携帯で動画を観れるようにもなってます。
思いがけずおもしろかったのが「森の虫松」先生の虫クイズ。実際に珍しいクワガタに触れながら子どもがクイズに答えるのだけど、先生の司会ぶりがうけます。
図書館の本もいろいろあって子どもより大人の方が夢中になれます。でも入館料大人1500円はちょい高め。地元なら年間パスポート3000円(だったと思う)にした方がよさそう。
地元に水族館がないというのは(動物園もつぶれて久しいし)寂しいことなので、日プラさんに感謝。それだけで夢虫館も応援したくなります。旧屋島水族館から流れてきたイトウの剥製は余計だけど・・・。
■せとうち夢虫館HP
■新屋島水族館HP
■日プラHP