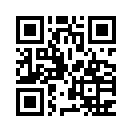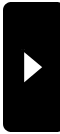2010年05月25日
「内田百閒の自選作品」
ブックオフで敬愛する内田百閒の古い本を見つけた。
『内田百閒の自選作品 現代十人の作家1』(二見書房)。昭和47年に限定2000部で発行されたもので、僕の購入した本は820番になっている。百閒は昭和46年4月20日になくなっているので、この本は死後に刊行されたことになる。自選の作品は、生前の備忘メモを元に編纂されたようだ。
40年近く前の本とは思えないほど、本がきれいな状態なのは二重の箱に守られていたおかげか、限定本故に書庫の奥に大事にしまっていた為なのだろうが、本当の理由は帯の惹句に戦いてしまったのでは、と思うほど大げさな調子で、今となってはそれがおかしい。
「その精確、その緊張。ここに文章
表現の極北がある。恥ずべき文章
の荒廃に堕ちた現代人は、もう一
度この恐ろしい人と会うべきだ!」
2009年12月18日
夢の釣り

ごくまれに釣りに行く夢を見ることがある。でもたいてい釣りをする前に夢から覚めてしまうのだ。
今朝もそういう夢をみた。はじめての川に着き、準備をして川岸に立つと、上流の方ではっきりとイワナがライズするのが見えた。夢の中だから、イワナが水生昆虫を補食するところが都合良くズームアップして見えた。なにしろイワナの斑紋やネイティブを表わすヒレピンの尾びれまではっきりと認識できたのだから・・・。
それで、釣りをはじめたら問題ないのだけど、そのポイントを同行者にゆずって僕は下流で移動するのだ。下流の流れは急に貧相になり、しかも滝のようになって、滝下を降りるのにちょっと骨が折れそうな感じだ。やれやれ、と僕は呟きながら滝の左側を降りていくのだけど、その途中で降りれなくなってしまう。身動きすらできない。無理して下降しようとした拍子にロッドティップを木の枝に引っ掛けてしまう。無理に抜こうとしてロッドは変な過重が掛かって、折ってしまう始末だ。それで竿先の折れた箇所を手にして途方に暮れていると、夢から覚めるのだ。
夢の中くらいは存分に釣りしたいのだけど、結局、一度もキャスティングすることすらなくて、目覚めは最悪だ。仕事にも行きたくなくなるのも当然だ。
“イワナのもっとも堅固な隠れ家は、「昔」の中である”との湯川豊は『イワナの夏』で書いているけれそ、夢の中でも、イワナはやっぱり記憶の奥の方に隠れているような気がする。
『イワナの夏』の続編ともいえる『夜明けの森、夕暮れの谷』をようやく手に入れて、すぐに読んでしまった。湯川豊の端正ですこやかな文章が、禁漁期で釣りに飢えた僕のココロに、静かに、深く沁み入る。深く沁み入ったのだけど、僕を夢の中で夢のような釣りに導くには滋養が足りなかったみたいだ。
『夜明けの森、夕暮れの谷』はフライロッダーズでの連載をまとめたものだと思っていたのだけど、巻末の初出一覧を見ると、そうでもなくてこの本に未収録のテキストの方がずっと多いことがわかる。それもまとめて本にしてくれないかな。そうしたら、きっと夢の中でも釣りができるに違いないのに。あの斑紋まではっきりと見えたイワナを僕のフライで誘いだし、そのぐりぐり動くイワナの手応えを感じることができるのに・・・。
2009年12月12日
釣れんボーイ

先日、『釣りキチ三平』のことを書いたのだが、他に釣りマンガといえば、『釣りバカ日誌』くらいのもので、1000万人を超える(ほんとに?)釣り人口のことを鑑みるとあまりに釣りマンガの歴史は貧相だ。
やはり釣りはひとりでするものだからなのか?「友情・努力・勝利」の方程式にはまりづらいのか?バス釣りをチーム対抗で魅せたりすればいいんじゃないか?それとも、僕が知らないだけなのか?
釣り少年たちと伝説の釣り師たちの5対5の釣りバトル(ルアー、フライ、餌釣りの釣り方やターゲットをかえれば組み合わせは無尽蔵だ)とか、魚がヒットした瞬間にギャラクティカマグナムみたいに火弾がとんだり、宇宙があらわれたりするような必殺技を身につければきっと盛り上がるに違いない。
そんなジャンプ的なマンガとは対極にあるけれど、釣りマンガの名作をひとつ思い出した。いましろたかしの『釣れんボーイ』だ。
売れないマンガ家“ひましろたけし”がときに釣りに没頭し、ときに日常を憂い、ときに妄想を膨らませるだけの、ぼんやりとしたマンガだ。鮎にのめり込み、東北から山陰、四国にまで鮎を追って遠征する。釣れれば尊大になるし、釣れなければ落胆して、肩を落としながら帰路につく。でもまた前のめりに釣りに出掛ける。
たいして売れていない(からなのか)、ひましろ先生はマンガを描くこともせず、釣りに行き過ぎる。ただただ、それがうらやましくて、自分が人生を誤ったかのような気もしてくるから、実は危険な思想書なのかも知れない。必殺技はでてこないけれど、釣りの悦びと無機質で淡々とした社会生活と、くだらない妄想には深く共感してしまます。
ぼーっと読むのに適してます。僕は分厚い単行本を持っているのですが、上下巻の2冊になった文庫本も出ています。
2009年12月08日
「釣りキチ旅日記」とアカメ

釣りのシーズンも禁漁にはいって2ヶ月が過ぎました。春まで、まだまだ長いので釣りに関する本を読んでいます。
「釣りキチ旅日記」は釣りマンガの金字塔「釣りキチ三平」の作者、矢口高雄が雑誌「つり人」に連載していたエッセイを集めたもの(発行は昭和61年)。
鮎釣りや渓流釣りはもとより、三平のシリーズの中でも興奮して読んだ覚えがあるブルーマーリンやキングサーモンダービーに、取材と称して挑んだ顛末もあってうらやましい限りです。キングサーモンの釣りには今は亡き西山徹氏も顔を出していて、腕が痛くなるほどキングサーモンを釣っています。キングサーモンもブルーマーリンも三平が釣った魚は桁違いのでかさで、その釣る迄の過程や、フックしてからのやりとり、そしてランディングしてからの勇姿(魚影)も全て印象的です。連載当時、僕は小学生で近所の用水路でフナくらいしか釣ったことがなかったのだけど、ブルーマーリンが死の間際に見せる神秘的な体色変化を、いつか自分の目で見たいと憧れていたのを思い出しました。
キングサーモンもブルーマーリンも遠い異国の釣りだったのだけど、四国にアカメという魚が棲むことを知ったのも「釣りキチ三平」を通してでした。実際にアカメを釣りに行ったわけではないけれど、連載と前後して、修学旅行で行った桂浜水族館で見たことはあるのを覚えています。怪物のような赤い目をした巨大魚が、同じ四国に棲んでいて、三平と真剣勝負をしたのかと思うと、なにやら誇らしげでもありました。心情的にはアカメを応援していたハズです。
今月のフライフィッシャーで備前貢氏がフライでそのアカメを釣っています。あんまり大きくて釣った備前氏自身、腰を抜かすほど興奮している様子が誌面から伝わってきて、30年たった今も怪物は怪物のままであったことに拍手を送りたくなりました。
2009年02月27日
コミさんの旅

『田中小実昌エッセイ・コレクション〈2〉旅 』(ちくま文庫)
雨ばかりの2月がもう終わろうとしている。まだちっとも具体化はしていないのだが、GWに家族で旅行に行く話が出ている。GWには毎年釣りに行ってたのだけど、たまには釣りを目的としない旅行もいいのかもしれない。
旅をテーマにした田中小実昌のエッセイを集めた文庫を読んだ。コミさんは旅が好きなのだが、その旅にまったく目的はない。旅がテーマになっているのだが、コミさんの旅は一般的な旅とは全然違う。観光地に行くこともないし、自分を探して放浪したりすることもない。旅に行くことさえまったく興味がないようにも思える。
知らない土地に着くと、その土地の飲み屋を探し、ぶらっとはいると何軒もはしごしながらずっと飲み歩いている。女のひとがいっしょのこともあるし、飲み屋で知り合って、いい感じになることもある。
だいたい旅のきっかけもなんとなく行き先もわからないままバスに飛び乗って、適当に乗り継いで、いけるところまで行ってみたりする。内田百閒のように鉄道マニアのひとは多いのだけれども(内田百閒もただ鉄道に乗って、行って帰ってくるだけの旅が好きだった)、こんな普通の路線バスに乗るだけのマニアの話はあまり聞いたことがない。
最後まで読んでしまったら、これらのエッセイの出典リストが並んでいるので、順番に読みたくなった。その本を手に入れたら、リュックに本を詰め込んで僕も旅に出よう。
やっぱりGWの家族旅行はムリだな…。
2009年02月23日
天狗になりたい

家に引きこもって黒田硫黄の『大日本天狗党絵詞』を読む。
息子はちょっと前に玉なしの自転車に乗ることができるようになったのだが、主人公のシノブが空を飛べるようになったとき師匠に「雲踏みができるようになったかシノブ。自転車のようにある日突然できるようになる」と云われる。シノブはその瞬間にひとでなくなり、天狗になったのだ。
ひとの世にまぎれた天狗たちの気高い思想は、黒田硫黄のマンガに対する気負いも含んだ意気込みとすっかり重なりあうようだ。天才だけが持つ孤独とマンガに選ばれた者の持つ恍惚が、黒く塗り潰されたページから登場人物や町や空の匂いを伴って溢れ出してくる。
一巻に登場する天狗たちはクールで恰好いい。僕も修行を積んで天狗になりたくなるほどなのだが、話が進み、天狗たちが伝説の天狗“z氏”を担ぎだし、日本を治めんと集結し徒党を組み出すに至って、気高さを失った天狗がどんどん堕落していくのが、物悲しい。
最近、表紙のデザインがかわって復刊されているので、それもやっぱり手に入れたい。