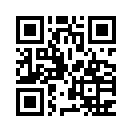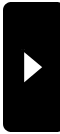2011年05月13日
『悪魔物語・運命の卵/ブルガーコフ』
『悪魔物語・運命の卵/ブルガーコフ (岩波文庫)』を読了。
ロシア文学といえば、皆なコートの襟をたて毛糸の帽子を被り難しい顔をして街路を歩いてるようなイメージがあります。それは聞き慣れないコロトコフやエヴグラフォヴナ、イパーチエヴィッチ・ペルシコフという名前をすらすらと読めないために、自分の眉間にも皺が寄って余計難しい顔になるのですが、ブルガーコフのこの2つの中編は名前のハードルさえ超えれば大丈夫。すらすら読めます。
特に「運命の卵」の後半は巨大化した蛇が暴れだし、B級ハリウッド映画的(もしくはハリウッド以外のパニック映画的)で、ロシア文学の小難しいイメージを一掃してくれます。
なにより「運命の卵」は革命後間もない1920年代にソヴィエトで書かれた中編SFなのに、現在の日本とあまりにリンクしているところが多くて、ストーリーよりもそっちの方が怖くなります。生命を活性化させる赤色光線はまさしく放射線だし、鶏が次々に死んでいく疫病は鳥インフルエンザや口蹄疫、供給の減った鶏(と卵)を赤色光線で増やしてひともうけをたくらむような人物は古今東西引きも切らず、些細なミスや意図的な手抜きによって大きなダメージを被ります。
読後に岩波文庫の表紙の写真を見ると、煙草をくわえたブルガーコフの黒い影の部分が、「ウルトラQ」のように渦をまきながら広がってきました。ブルガーコフの長編『巨匠とマルガリータ』が、池澤夏樹が編集した世界文学全集にラインナップされています。
2011年04月24日
『NARUTO 巻ノ55 〜大戦、開戦!〜/岸本 斉史』

震災の影響で発売が遅れていた『NARUTO』の55巻がようやくリリースされました。今巻ではいよいよ第四次忍界大戦が開戦します。
これまでのキャラクターが総動員といった感じでプロレスオールスター戦状態なのですが、それぞれのキャラクターがそれなりに闘いを魅せるだけで、詰まんないです。とうに死んだキャラがカブト(嫌い!)の穢土転生によって生返り、しかも操られ、それなりのページを使って闘います。木の葉や砂の忍者はともかく雲や岩の忍者を続々と登場させた尻拭いのような巻です。ちゃんと個性を与えられた新しいキャラ達の活躍の場をつくるための仕掛けとして、大好きなデイダラやサソリが、劣化コピーのような形で彼らと対峙することになります。クローンゼツが相手では、せっかくの新キャラ達が活躍する場面がなくなるのは理解できるのですが、この後、イタチやペインさえもカブトの術の言いなりになるのはどうにも受容できかねます(それに旧五影や多数の忍者のDNAを集めながら、自来也は無理っていうのは都合よすぎます)。
かってのマダラはたったひとりで、木の葉に挑み、それが何より伝説となったのに、16年前の轍を踏まないように“暁”を組織し、入念に準備してきた陰謀が露になり、陰謀が陰謀でなくなった結果、そのマダラの強い復讐心すら、分散され薄められたような気がします。濃密な個々の戦いがメインだったこれまでの『NARUTO』が組織の戦いになった途端隙だらけになったようで残念です。だいいち忍者は“しのぶ”者であるはずです。大勢が集まって軍隊にように正面からぶつかりあうと、その時点で忍者としてのアイデンティティを失いその個性を発揮できないのは当然の結果です。
ジャンプの連載でもまだ当分はこの流れが続くでしばらくは辛抱しなといけません。
2011年04月20日
『イエメンで鮭釣りを/ポール・トーディ』
『イエメンで鮭釣りを/ポール・トーディ』(白水社)を読了。
サクラバさんのブログに紹介されていたのを読んで興味を持ち購入。イエメンに鮭を放流するプロジェクトの顛末を描いた作品。イエメンの釣好きの富豪シャイフが夢みた鮭を故郷の川に導入する計画に巻き込まれるイギリスの学者、アルフレッド・ジョーンズ博士とエージェントのハリエット、首相官邸広報のピーター・マックスウェルの物語。それぞれの間で交わされる手紙やeメール、日記や議事録などの文書から構成されている。
イギリス人の作家によるイギリスが舞台の物語だから当たり前なのだが、イエメンの富豪シャイフの回想や日記はそこに挿入されていない。博士との会話に彼の考えの一端が示されるだけだ。戒律の厳しいイスラムに釣りという娯楽の導入を夢想するのだが、その理想は結局のところ金持ちの道楽としか受け止められず、アルカイダに命を狙われてしまう。
イスラムであっても、権力と金を手にすれば戒律は緩み欲望が優先され、腐敗するのは歴史にある通りだ。博士から見たシャイフは、異教徒のもつ神秘性をもちながら、一方で親しみやすく魅力的な人物に描いているけれど、実のところエジプトやチュニジアで国を追われた元首とそうかわりない。そしてそれが釣りを文化と称して、植民地に鮭や鱒を放流してきたイギリスという国の思惑と結託し、共犯関係を結ぶのだ。
そのプロジェクトの馬鹿馬鹿しさと、同じ趣味を持つ共感により、楽しく読んだのだが、釣りをする人物がいかにも善人であるように描いているのが、気にいらない。僕もそうだけど、釣りをする人間ほど独善的な人間はいないのだから。いつだって、ひとより自分が優れた釣りをすることしか考えていないのだ。シャイフだって自分の釣りのためだったら、お金に糸目をつけず砂漠に川を作ってそこに鮭を放流しようとするくらいなのだ。どうせなら腹黒い欲望にまみれたシャイフの側からの『イエメンで鮭釣りを』を読みたい、と思う。
2011年04月17日
『アンビエント・ドライヴァー/細野晴臣』
『アンビエント・ドライヴァー/細野晴臣』(マーブルトロン)を読了。
90年代半ばと00年代半ばに細野さんの雑誌連載をまとめた1冊。細野さんの優れた仕事のなかで、僕にとっては最もピンとこないアンビエント時代のアンビエントなモノローグといった感じで、特に前半(90年代半ばの方)は退屈だった。ニューエイジだとかネイティブ・アメリカンだとか、まったく興味がないわけではないのだが、ミュージシャンがそういうこと言い出したときは注意が必要だ。音楽(ロックやポップス)は高尚になればなるほど詰まらなくなるから。どおりで90年代の細野さんの仕事がピンとこないわけだ。
それで90年代後半から現世に引き戻されたように昔の仲間たちとハリー&マック(久保田麻琴)やティンパン(鈴木茂、 林立夫)、スケッチ・ショウ(高橋幸宏)とまた嬉しい作品のリリースが続く00年代の方は、その内容も音楽的なエッセイが増えて嬉しい。スケッチ・ショウのステージで高橋幸宏の助言に従い眉を細くしたところ「意地悪そうだ、怖い」感じになったエピソードとか、気味が悪い細野さんの姿がイメージできて楽しい。
そうして読み終わってみると、前半のところも読むタイミングが悪かったのだと思う。90年代の文化や、ニューエイジがちょっと古くさいイメージになっている現在より、90年代が見直されたとき(70年代や80年代がリバイバルしたように)に細野さんの仕事を振り返りながら読むとまた別の発見があったのかも知れない。
2011年04月12日
『アメリカ―非道の大陸/多和田葉子』
『アメリカ―非道の大陸/多和田葉子』(青土社)を読了。
多和田葉子は好きな作家のひとり。『アメリカ』は“あなた”とよばれる主人公(?)がアメリカを旅する短篇集。アメリカのいろいろな都市で、街で、郊外で、砂漠で、飛行場で、ホテルで誰かと出会い、物語がはじまりそうな気配が濃くなったり、うつろになったりする。その気配の濃淡を描く掌編だ。
わりとさくさく読めるのだけど、言葉はその速度のまま僕の中を通り過ぎていって、僕の中に具体的なものは何も残らない。ぼんやりと、本を読んだという事実のみが所在なく佇んでいて、退屈なロードムービーを観たあとのようだ。
退屈なロードームービーなんて、本当は観たくもないのだけど、退屈でないロードムービーなんて、実はロードムービーでもなんでもないので、やはりここでの“退屈な”というのはこの小説を読む上でも大切なキーワードに違いない。ジム・ジャームッシュの『ストレンジャー・ザン・パラダイス』みたいに。
2011年03月29日
『本日記/坪内祐三』
『本日記/坪内祐三』(本の雑誌社)を読了。
「本の雑誌」に連載されている「坪内祐三の読書日記」をまとめたもの。本屋と古本屋とCDショップを巡り、本を読み原稿を書いて、東京の町を散歩したり、電車を乗り継いだり、定食を食べたりする日記。ときどき蘊蓄と雑感と揶揄と攻撃と批判と自慢があって、主に毎朝トイレの中で読んだ(この頃、息子もトイレに本を持ち込んで、たいてい30分近くでてきません)。
毎日、ブログを書くのはけっこうたいへんで、時間がかかってしようがない。僕も「今日はジュンク堂とブックオフで本を買い、コンビニでスピリッツとジャンプとヤンマガとプレイボーイを立ち読みし、中古CDショップに立ち寄って欲しかったアルバムを見つけたけどたいして安くなっていなかったので、棚に戻した。夜にはカレーを食べて、ビールを飲んで、寝る迄本を読んだ」みたいな日記をつけていたこともあるのだけど、それだと全く仕事をしていないひとみたいなので、それはこの公開されたブログでは書けなくて毎日別のネタを探している。
それにしても2002年の5月24日のテキストの注釈にある「2005年に買ったというボブ・ディランの9枚組のスペシャル・ブートレグ」って、どのアルバムのことだ?本当の海賊盤なのだろうか?去年リリースされたモノ・ボックスの8枚組よりまだ多いなんて・・・。