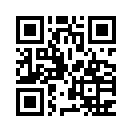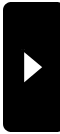2012年01月31日
渓流・清流を探ねて―つりと人生 三浦 秀文
『渓流・清流を探ねて―つりと人生/三浦 秀文』(青林書院)
近所の古本屋で見つけた昔の渓流釣りガイド本。発行は昭和30年(1955年)。傷みの激しいカバーは、物干し竿のような竹竿で鮎を狙うモノクロのグラビア。著者の三浦 秀文さんは中部日本新聞の編集局長から、ドラゴンズの取締役もつとめたひと。
前半はこの著者の釣りエッセイ。釣りのおかげで人生救われた的な内容。後半に関東から関西までの各地の漁協や市区町村から集めた渓流・清流の情報が記されている(鮎の情報がメイン)。釣れる魚の種類や、解禁日、入漁料、交通手段、宿泊施設の案内まで充実している。
なにしろ昭和30年のことなので、御母衣湖(1961年完成)や九頭竜湖(1968年完成)をはじめとした、各河川のダムはなく、川の上流と海がちゃんと繋がっていた時代なので、釣れる魚としてヤマメよりもマス(サクラマスやサツキマス?)の方がよく紹介されている。そして、奥まった川の上流までは最寄の駅からバスで2時間とか、3時間とかかけて行かねばならないのだ(さらに徒歩で1〜3時間という表記もあり)。
道路事情も今とは比較にならなかったはずだし、マイカー率の低かったこの時代、バスはおそろしく辺鄙な集落まで路線網をひろげている(JR、いや国鉄も今よりずっと豊かな路線をもっていた。最近本屋で「鉄道地図 残念な歴史」という本を見つけた)。当然、そこまで行くと日帰りは無理で泊まる必要があるので、小さな集落にも民宿があって、数百円で泊まることができる。ちなみにヤマメやアマゴの日券も200~300円程度、鮎は500円が相場だ。また地域によっては、漁業組合員でないと釣りができず、それも毎年入札で、各組合員が釣ることのできる流れを振り分けるところもあった。
そういう情報が淡々と並んでいるだけなのだが、山の奥まったところ、川の支流のまた谷沿いの小さな集落にも、ひとが暮らし生活をしていた様子が感じられる。宮本常一が『忘れられた日本人 』で活き活きと描いたようなひとの営みがあったはずなのだ。しかし、この本で紹介されている集落のいくつかは、高度成長とともに過疎が進んだり、ときにはダムの底に沈んで地図からその名が消えてしまったのだ。
今、僕たちは国鉄とバスではなく、高速道路を乗り継ぎ京都から3時間、4時間で渓流の一番奥まで到達することができるようになった。そして便利にはなったけれど、想うような魚は、けっして想うようには釣れないのだ。
今年のシーズンもいよいよ解禁が近づいてきた。この本では、石徹白川の項に以下の表記がある。
この地方は渓流魚の宝庫として揖斐川上流地帯(徳山、坂内、藤橋各村)、庄川上流地帯(荘川、白川、平各村)及び益田川上流(高根、朝日村各村)とともに全国屈指の釣場であろう。
禁漁になってすぐには半年は長いと思っていたけれど、ここまでくれば春はもうすぐだ。今年もまた大物を釣る夢想をしながら、何度も川へ向かうのだろう。
2012年01月08日
『ナイロン100%/ばるぼら』
『NYLON100%/ばるぼら』(アスペクト)を読了。
80年代のポップなトーキョーの情報発信サロン的な伝説のカフェ“ナイロン100%”の全貌を、そこに関わった人たちへのインタビューで描き出した80年代ニューウェーヴ世代にはたまらないエピソード満載の一冊です。なにしろ戸川純がアルバイトをしていたという伝説のカフェなのです。それだけでトンガリキッズに憧れていた僕はムネのコドウが早くなります。
前に読んだ『ストリート・キングダム/地引雄一』の東京とはパラレルの80年代のトーキョーがあって、それぞれがそれぞれに偶然にではなく、必然的にナイロン100%に集まり、トーキョーの中でもひときわ人工的なネオンの明りを明滅させていたのです。そしてその灯りを道しるべとして集まってきた人たちによって、さらに常夜燈としての役割を果たすようになっていきました。
“ナイロン100%”でライブを行ったヒカシューの巻上公一や81/2の久保田慎吾、ハルメンズのサエキケンゾウ、戸川純、Phew、ゲルニカの上野耕路、さらに有頂天のケラや大槻ケンジに至る日本のニューウェーブシーンを彩る多彩な面々に加え、歴代の店長やスタッフ、客としてナイロンに通っていた常磐響、先の地引雄一や当時の宝島編集長関川誠まで登場して“ナイロン100%”とその時代を多面的にあぶり出していきます。
それはもう青春のキラメキ以外のなにものでもありません。
そしてニューウェーブをひとつの価値判断の基準としているような、ネクラな僕にとっては、やっぱりそのキラメキは眩し過ぎるのです。
あー、あと各見開きの右隅にナイロンの推薦するニューウェーブ系のレコードジャケットが150枚以上も掲載されていて、あれもこれも欲しくなってたまりません。
2011年11月25日
『NARUTO 巻ノ58 〜ナルトVSイタチ〜/岸本 斉史』
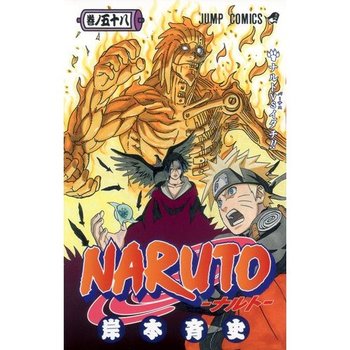
まだまだ続く第四次忍界大戦。遂にイタチ&ペインがナルト&キラービーと遭遇し、イタチがナルトに仕組んだシスイの目を持つカラスによる“別天神”によって、イタチが穢土転生の術から自由になるというどんでんがえしはあるのですが、やっぱりこの巻も全巻を覆う穢土転生が気にいりません。
あげくのはてにナルトまでが「・・・このエドテンとかいう術・・・気に食わねェ!」という始末。読者のみならず、都合よく死人が甦る穢土転生に作者も困っているのではないでしょうか。
そしてイタチ(須佐能乎!)をくわえたナルト&キラービーとの3対1とはいえ、ペイン(=長門)がたいした見せ場もなく封印されてしまいます。きっと自来也も草葉の影で泣いてます。かっての五影達だって、本編ではなく外伝として描けばそれぞれのキャラクターをもっと活かせそうなのに(無とオオノキの土影子弟物語なんか・・・)。
あとトビ(
そして既にジャンプの連載では、マダラまで穢土転生で出現する始末です。そうなると、問題なのはマダラの名を語るトビの正体なのですが、僕は“六道仙人”では?と思うのです。ここまで伏線をはっておいて、トビの正体が全くの新キャラというのは考えにくいし、マダラと同格か、それ以上となると、伝説の“六道仙人”以外考えられません。
うちはの石碑は、輪廻眼がないと全てを読解することは不可能ということは、その碑文を残したのはおそらく“六道仙人”なのでしょう。そしてそこには無限月読により、世界全体に幻術をかけるのと同時に、“六道仙人”自身の完全復活が記されていたのでは?十尾を集めるトビの真の目的は、“六道仙人”の復活なのに違いありません。なので、正確には“六道仙人”の残留思念のようなものの集合体がトビの正体ではないかと、思う次第なのです。
2011年11月05日
遊歩大全!

最終日の午後、ふらっと立ち寄った古本まつりでバックパッカーのバイブル的超レア盤「遊歩大全/コリン・フレッチャー」の上下巻セットを500円で見つけてしまいました。一瞬、5,000円の間違いだと思って目をこらしたのですが、やっぱり500円。悪いことでもしてるかのような気持ちでレジに持っていきました。
「遊歩大全」がアメリカで出版されたのは1968年。森林書房から芦沢一洋さんの訳で発売されたのは1978年。僕はフライフィッシングライターとしても活躍した芦沢一洋さんの本をネットで探していて、この本のことを知りました。古書価格やオークションでは1冊5,000円くらいで取引されていて、ガケ書房の古本イベントでも見かけたことがあるのですが、セットで8,000円もして、とてもレジに持っていこうという気にはなれませんでした。
見返しのページに書き込みがあって、そのせいで安かったのかも知れません。レジに持っていったら古本屋のおじさんも、「お、いい本みつけたね」とほめてくれました。
書き込みから前の所有者も大文字を望むこのあたりに住んでいたことがうかがえます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10.August.78
(2)馬とヨット・・・一生やること。
(1)創造すること・・・仕事でものをつくり出すたのしみをもつ
(3)禅
年寄って(海の見える)海辺の小屋で生活すること。
馬・・・生物との係り
ヨット・・・自然との係り
この夏休みの間、朝5時半起床、大文字参り、食事、馬
2011年06月12日
『NARUTO 巻ノ56 〜再会、アスマ班〜/岸本 斉史』

55巻から1ヶ月半の短いインターバルでナルトの56巻がリリースされました。週刊連載恐るべしです。数年に1回しかアルバムをリリースしない海外のアーティストと比較すると明らかに日本のマンガ家は働き過ぎです。この巻のように今後のストーリーへの伏線もなく、新しいキャラが活躍の場を与えられるだけ戦闘シーンが延々と続くのも仕方がないのかも知れません。
前巻からの第四次忍界大戦の戦闘シーンが続くだけで、それ以上のことは起こりません。九尾のチャクラをもつ金角銀角のコンビも、忍刀七忍衆よりもキャラとしてはたっているのに、大戦の中のひとつのシーンでしかないので、わりとあっさりやられてしまいます。だいたい穢土転生で甦っているだけなので、彼らが与えられたシーンは最初から限定的です。そしてアスマを生き返らせたばっかりに、アスマ班の戦いが描かれるのですが、金角銀角以上に全く意味がありません。チョウジの成長なんか今さらどうでもいいです。それとも彼の成長がナルトとサスケ、マダラと九尾の関わりになんらかの影響を及ぼすことがあるのでしょうか。
とにかく忍者が多過ぎます。うじゃうじゃ多過ぎて、うっとおしいくらいです。そんな中で侍大将であるミフネだけが、この巻のなかで真剣の輝きを魅せてくれます。五影会議のときに初めて出てきたときには、また中途半端な顔のキャラが出てきたと思ったのですが、こういう脇役にちゃんと個性のあるエピソードを描くことがナルトの物語に歴史と深みを与えています。
ようやく修行を終えて、戦線に復帰するナルトに期待するしかありません。そしてイタチの眼を移植され、しばらくその姿を見ないサスケはどんな風に変わるのでしょう?
2011年05月28日
『ストリート・キングダム/地引雄一』
『ストリート・キングダム〜東京ロッカーズと80'sインディーズシーン〜/地引雄一』(K&Bパブリッシャーズ)を読了。
69年生まれの僕は東京ロッカーズが盛り上がっていた70年代の後半はまだ半ズボンをはいて虫採りに夢中になって走り回っていた小学生だった。それから10年経って大学生になった頃、宝島でそんなムーブメントがあったことを知った。フリクションとかリザードとか興味はあったけど、日本のバンドより洋楽の方に惹かれていたので、音源を探すこともなかった。
この本を買ったのは、そのフリクションやリザードやS–KENらの未発表ライブのDVDが付いていたからなのだが、それよりも300ページの本の1/3を占める当時の写真の方がずっと素晴らしく、音はわからなくても、当時の熱を感じることができる。それはライブシーンの写真よりも、なんでもないスナップ写真の方が鮮明だ。
東京ロッカーズの真ん中にいた世代は、それ以前から音楽活動をしていたのだが、いったん挫折を経験した後にパンクと出会っている。挫折を味わった苦さと、それでも音楽しかないという強い決意のようなものがその眼差しから伝わってくる。
東京ロッカーズと呼ばれたムーブメントはほんの数年で終わったのだが、そのシーンに感化された恐れを知らない若者たちにその熱は受け継がれインディーズブームで一気に爆発するのだ(そして資本に取り込まれた末にバブル崩壊と共に瓦解することになる)。
テキストはその歴史(特に勃興期)を丹念に追ってはいるのだが、100ページも写真に使っているので、分量が少なく物足りない感じもする。著者がまえがきで述べているように、著者自身が実際にそのシーンの中で体験したことのみがベースとなっているので、仕方がないのか・・・。
しかし、この本でしか見れないようなライブのちらしなどの多くの図版類は貴重だ。今みたいにパソコンで手軽に作れるものではないので、バンドやイベントの特徴が表れていて眺めているだけで楽しい。ちらしも100ページくらい欲しいくらいだ。