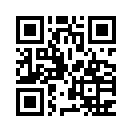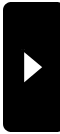2012年08月11日
夏の古本まつり 2

今日の成果はこの六冊。内田百閒は僕の定番。川村二郎の本にも内田百閒論が収められています。あと山の本も一冊。
釣りの本はピンとくるものが見つかりませんでした。
どれも200〜500円と下鴨らしく安く購入。あと奮発して高い本も一冊欲しかったのに、午後から足下が水没するほどの激しい雷雨に襲われ撤収を余儀なくされ残念。
もしかすると16日の最終日にちょっと行くかもしれません。
2012年07月22日
『ドラゴンは踊れない /アール・ラヴレイス』
『ドラゴンは踊れない /アール・ラヴレイス』(みすず書房)
本の帯に書かれた“ドラムが鳴り、抵抗のダンスが始まる。世界の片隅に生きる人々の希望を賭けて、バンドマン、スラムのごろつき、そいて恋する者達が踊る、カリブ海文学の傑作”という惹句に惹かれて買った本書。
読み始めてすぐ、序章の終わりに次のようなテキストがあって、期待が高まる。
ダンス!カリプソにはダンスが宿っている。ダンス!歌が近所の人の死を悼むものだとしても、音楽があくまでも踊れ、という。兄弟が巻き込まれたやばいもめ事についての歌詞であっても、音楽が踊らなきゃ、というのだ。痛みを称えて踊れ。ダンスしろ!毎日死にそうなほどひどい目にあってるって、じゃあ踊れ、政府は知らんぷりだ、なら踊れ!女が金をもってほかの男と逃げた、さあ踊れ。踊れ、踊れ、踊れ!踊りには邪悪なものを退け、自分を守る力がある。ダンスは悪魔の力を断ち切る、呪文なのだ。ダンス!ダンス!ダンス!カーニヴァルがこの丘の谷という谷すべてに、この力強いダンスをつれてくる。
そして登場人物の魅力的なプロフィールが過去から現在まで章ごとに丁寧に描かれ、中盤までは、期待以上に期待がふくらんで、時代背景や作品世界を深く理解するための解題に目を通すのももどかしい程に、先へ先へとページを繰ったのだが、中盤以降“抵抗のダンス”は尻すぼみする。狂騒のカーニヴァルは夜明けとともに終わりを迎えるのだ。
解題や解説にも書かれていたように、この作品の舞台となったトリニダード・トバゴでは、自治権の拡大とともに自然な独立(いろいろな差別や貧困の問題があったにせよ)が達成された島なのだ。流血の革命により力づくで権力を勝ち取ったわけでないのだ。
物語のクライマックスで、振り上げた拳(それは気分だけの革命行為)も誰かに突きつけられることもなく、そのままゆっくりとおろされる始末で、帯の惹句はまったくの空回り状態で、過去と現在と未来が反復されるリズムのように繰り返されることを示唆している。タイトル通り『ドラゴンは踊れない』ままなのだ。
しかし、物語全体をゆるやかに包む倦怠と徒労は、この愛すべきルードボーイ達のどん詰まりの人生を肯定も否定もしていない。少しの運と、少しの努力で彼らの未来は一変する。同じように反復されるスティールパンの音だって、まったく同じ音、同じリズムが永遠に続くことはない。いつだって新しいリズムが、新しい音楽とダンスを作るのだから。
2012年05月19日
『NARUTO 巻ノ60 〜九喇嘛!!〜/岸本 斉史』

60巻では二尾から九尾まで尾獣が勢揃いです。二尾・三尾・五尾・六尾・七尾と八尾・九尾が相対するのを見て、“怪獣総進撃”とガイが思わず呟いてしまったのですが、尾獣と尾獣化した彼らの姿に、忍の面影はどこにもありません。19巻で自来也が「忍者とは忍び堪える者」と大蛇丸に語った言葉からは、何万光年も遠く離れてしまいました。忍びと忍びの個人の戦いはすっかり様相を変えていましまいた。GWにちょっと読み返したのですが、サソリ対チヨバア&サクラの戦いや、デイダラ対サスケの美しい術の凌ぎあいから、本当に遠くまで来てしまいました。
尾獣勢揃いにより、修行によって手に入れた強さとは全く次元の違うところで、戦いが継続していきます。強さのインフレ(紛うことなきハイパーインフレです!)化は加速度的にすすみ、カカシとガイでさえ、すっかり置いてけぼりをくってしまっています。尾獣たちの戦いの場に居ることが、まったく不自然でなりません・・・。
そして、不満の第一等は、九尾(=九喇嘛)とナルトの和解です。狂気と暴力の神である九尾が、聞き分けよくナルトにチャクラを与え、共に戦うなんて興醒めもいいとことです。
いやはや、僕にはちっともおもしろくありません。穢土転生以来、ナルト世界にはまることができません。クライマックスに向けて、徐々に片をつけていくはずの展開が、僕にはちっともココロに響きません。
その中で唯一ぐっと来たのが若きオオノキに掛ける初代(?)土影の言葉です。
「肝心なのは/己の中の/意思じゃ(中略)壁に当たるうち/それを捨て・・・/言い訳し/かわりに憎しみを/拾うことになり/かねん」
村上春樹がエルサレム賞を受賞した際の「壁と卵」のスピーチにも通低するような強い言葉です。前巻でマダラの落とした巨大隕石を、ひとりで受け止めようとしたオオノキの勇気を支えている師匠の言葉です。
そういえばオオノキが巨大隕石を受け止めるシーンを僕は何処かで見たことがあると感じていたのですが、最近それが何なのかはっきりと思い出しました。戦闘メカザブングルでジロンが、巨大ミサイルをウォーカー・ギャリアで見事受け止めるシーンです。ジロンの行動もオオノキのそれも、男の子の無鉄砲な勇気というしかない快挙でした。オオノキの場合は、さらに巨大隕石の追い打ちがあって、勇気は打ちのめされたのですが・・・。
それでもオオノキは再び立ち上がります。倒れても倒れても、彼の意志は言い訳を許しません。そして「塵遁・限界剥離の術」で自分より若い五影たちを鼓舞するのです。
2012年05月03日
古本の神様
恒例の「春の古書即売会」。京都の古本祭りが今シーズンも開幕しました。今年の成果は写真の通り。
『渓流1985』は古本祭りで、いつも注意して探してる渓流釣り関連の本。棚に並んだ本の背中を目で追っていると“源流”などに反応してしまいますが、『カメラの源流を訪ねて』だったりします。“ヤマメ”だと思ったら“ヤヌス”だったり・・・。
開高健の『私の釣魚大全』は文庫をもちろん持っているのですが、 他にも数本釣りエッセイが追加されています。で、しめしめと思ったのですが、チェックしてみると既に持っている『開高健全ノンフィクション 河は眠らない』にどれも収録されていました・・・。
笙野頼子とブローティガンの小説と岡崎武志の古本本はわりと安かったので購入。そして敬愛する内田百閒の戦前の単行本! 旧仮名遣いの内田百閒をコンプリートすべくこちらも古本祭りでは最優先のターゲットです。この『丘の橋』の他に数冊、数千円のも見つけましたが、ちょっとそれは手が出ませんでした。
そして、古本の神が、僕に微笑んでくれた今日の逸品は、大友克洋の『ヘンゼルとグレーテル』です。いつもはあまり注意して見ることのない絵本のコーナーで発見しました。奥さんに絵本のいいのがあれば、と頼まれていたのが幸いしました。絵本好きそうな女性がえらい熱心に本を探していたので、奥さんにもお土産をと思ってその脇に並んだところ、太ゴシックのタイトルと大友克洋の名前があざやかなグリーンに白抜きで目立っていて、そこだけ周りから浮き上がり輝いて見えました!すばらしい!!本当にすばらしい。ワンダフルな気持ちです。
ちなみに奥さんへの絵本は見つかりませんでした・・・・。みやこめっせでの「春の古書即売会」は5月5日までです。
■京都古書研究会
2012年04月15日
『山漁 ~渓流魚と人の自然誌〜/鈴野藤夫』
『山漁 ~渓流魚と人の自然誌〜/鈴野藤夫』(農山漁村文化協会)
タイトル通り渓流魚“ヤマメ・アマゴ・イワナ”と人との関わりについて広範に書かれた本。目次は以下の通り、「渓流魚の博物誌」「魚止考」「渓流魚の漁法」「保存と食法」「渓流魚の伝説」「職業漁師」「伝統釣法」「渓流魚の民俗」「釣魚余談」「川虫の民俗」となっており、渓流釣りをするひとなら何処から読んでも興味深い内容になっている。
江戸時代を含む多くの川や魚に関する文献を引用し、また1000ヶ所以上を訪れたという渓流釣りを通し、実際に見聞した内容を盛り込んでいる。そこで思うのが、いつものことであるが、かっての渓流の個性的で豊潤な姿だ。川の流れは決してとどまることがなく、瞬間瞬間違った様子を見せている。それ故、地域によって違った漁法が発展するのだ。同じ景色などどこにもないのだ。しかし林道の開発、森林の伐採、堰堤の設置と、ひとは目先の経済的な利益だけを目的に、“便利”を旗頭に掲げて全てをフラット化してきたのだ。
著者の鈴野氏は昭和21年生まれ。都市から農村、山間部へと開発の進む日本の高度成長とときを同じくして成長してきた。そしてそれは文献だけでなく、各地域に残る文化をギリギリ取材できた世代だ。僕が釣りをはじめた頃には、車でどこへでも行けるし、どんな山奥の谷にも堰堤があって、その脇に伸びる林道を歩くことができたのだ(そしてそれを釣れない理由にしてきた!)。
といった僕の愚痴はともかく、内容はすばらしくどのエピソードも興味深い。なかでも“滝太郎”や“漁師を呑んだ大イワナ”の項がある「渓流魚の伝説」は釣り人の夢を際限なくかき立ててやまない。今も、深い山奥の大きな淵の底には大イワナが居るに違いないのだ。
日本は、その国土のほとんどが山地で、しかも年間を通して雨がよく降る。それは、この国に豊かな渓流があるということだ。平野部で育った僕には、コイやフナのような魚がひとの生活圏内と同じところに居て、密接に繋がっているイメージがあった。渓流釣りをはじめるまでは、イワナやヤマメは『釣りキチ三平』の中と、人が稀にしか足を踏み入れないような山深い谷の奥にのみ生息するものだと思っていたのが、渓流魚もひとの生活の近くに棲み、それぞれの時代にそれぞれの暮らしと密接な関係があったのだ。全編を通じて、人と渓流魚のつながりについて、理解を深めることができる好著だ。
鈴野氏には他に『峠を越えた魚―アマゴ・ヤマメの文化誌』や『魚名文化圏 イワナ編 』などもあって、ぼちぼち探して読みたいと思います。
2012年03月03日
『NARUTO 巻ノ59 〜五影集結…!!〜/岸本 斉史』

穢土転生によって、いよいよマダラまで甦ってしまいました。しかも輪廻眼まで開眼して圧倒的な強さを見せつけるのですが、よりによって彼もカブトに操られるゾンビでしかないのです。伝説の忍びも地に落ちました。そして彼に立ち向かうのは、最強のはずの五影です。その五影が五人そろってようやくマダラと、とんとんだなんて…。1対5の時点でなんだかなぁという感じです。しかもマダラは所詮ゾンビなのですから。
それでも五影が、見開きページで並び立つシーンは圧巻です。ジャンプ連載当時はコンビニで立ち読みしながらちょっと感動しました。そして土影オオノキの矜持だけがこの長くて寂しい戦いを支えています。一尾を抜かれ、暴走しない我愛羅なんて、感情に乏しくてちっとも肩入れできません。
そして肝心のナルトは、ついにトビ率いる人柱力六道と相対します。生身(?)のトビも、やっぱり穢土転生で甦った人柱力を操っているので今イチ感心できないのですが、もう少しです。あと少しで穢土転生の術は一掃されるはずです。