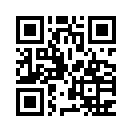2007年02月18日
琵琶湖の鮎とダム
先週のキャンプ、琵琶湖の朝は穏やかでした。静かな波が打ち寄せ、岸の近くを漁船が何台か通りすぎました。小鮎をとっているのだとUさんが教えてくれました。北小松にある小さな桟橋に船を寄せ、トラックの水槽に運び込んでいるようでした。
琵琶湖で獲られた鮎はしばらくの間、業者の池で養殖され、5月頃に全国の河川に運ばれ放流されます。
琵琶湖の鮎は、基本的に河川に昇ることなく体長も10センチ程度にしか成長しないのですが、河川の放流されると、20センチを超える普通の鮎に成長します。
日本の河川にはたいていダムがあって、河口と川の中上流域をいききする鮎の遡行が妨げられているので、琵琶湖産の鮎は全国に放流されています。鮎はお金になるので、各河川の漁協は熱心に鮎の放流をおこなっています。
ブラック・バスの放流による環境への影響は口うるさく喧伝されていますが、鮎の放流についてはおおきく取り上げられることはほとんどないようです。その川に累々と伝わってきた固有の遺伝子があるのですが、琵琶湖産の鮎が放流されることにより、ほんとうのネイティブは姿を消していきます。もちろんダムができた時点での環境への影響の方がよっぽど大きいのですが・・・。
ダム反対を掲げていたはずの嘉田滋賀県知事は先日の県議会本会議で治水対策の有効性を踏まえて、ダム建設を容認すると、その方針を転換しました。淀川水系のダム建設反対を答申した淀川水系流域委員会の活動は休止になったばかりのことだし、どうもダム建設推進派の巻き返しがはじまったようです。
琵琶湖の北部に流れ込む高時川に予定されている丹生ダムの建設がふたたび動き出すのでしょうか・・・。
2006年11月13日
虹の大文字。
大文字から見る京都市内のほうを見下ろすと、広大な影の部分に光が射してなかなかきれいでした。風が強く雲がはやく移動するので光の位置もそれにあわせて北西から北東の方で動いていきます。
しばらくして時雨れてきたので、早々に山を降りることにしたのですが、ちょうど岩倉の上空あたりに淡い虹があらわれました。

2006年11月05日
紅葉のはじまり。
いつもの公園へ遊びにいくときれいに紅く染まった桜の葉っぱが落ちていたので自転車のかごに入れて持って帰りました。
もみじの紅葉はまだなのですが、白い壁に夕日を受けたもみじの影がうつっていました。
2006年07月22日
冬虫夏草と芦生の森。
雨は午前のはやい時間で止んだので、息子が参加した「京都造形芸術大学こども芸術大学」の『本と手をつないで子育てしたい2006』では雨あがりの瓜生山を短い時間だが散策したそうだ。
大きな虫眼鏡を手にした講師の久山喜久雄さんを先頭に、30組の親子が虫や植物に目をこらしながらゆっくりと山道を歩いた。息子はもちろんだけど、母親も冬虫夏草のクモタケ(蜘蛛から生えてます)を見つけたりして楽しんだみたい。
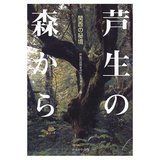 ところで、昨日の京都新聞に美山にある京大の芦生研究林(演習林から呼び名がかわった)の滋賀県側からの入山が禁止になったという記事が載っていた。
ところで、昨日の京都新聞に美山にある京大の芦生研究林(演習林から呼び名がかわった)の滋賀県側からの入山が禁止になったという記事が載っていた。
滋賀県、福井県との県境に広がる芦生の森は大正10年から京大の演習林として使用されている広大な原生林だ。
由良川の源流部に自然の森が広がっている。下流部に事務所があって入山者の管理をしているのだが、演習林の北東にあたる滋賀県との県境にある地蔵峠からも入山できるようになっていた。かっては地蔵峠の手前まで車でいくことができた(数年前に峠のずっと手前にゲートが設置されそこから30分ほど歩いて峠を越えるようになったらしい)。もう10年近く前のことだが、ボクは何度かそこから演習林にはいり、由良川の源流にそって1時間位歩いたところから、釣りをしたことがある。
何度か釣り雑誌でも見たことがあるし、わりと有名な釣り場だったのだけど、釣り場まで最低でも1時間は歩かないとたどりつかないので、京都府内では珍しく春先を過ぎても魚が残っていた。
しかし、釣りをしながらもなんとなくここで釣りをしても大丈夫なのだろうかという心配はあった。まったくの手つかずというわけではないけれど、しっかりと管理され守られている森を守ったほうがいいのではないかという思いは持っていた(もちろんそれよりも魚を釣りたい気持ちの方が強かったから1時間も山道を歩いたのだが・・・)。
釣り人だけではなく、山歩きでの入林ももちろん多く、『入林者の増加に伴う歩道(周辺)の拡大と踏み固めにより、森林の荒廃が急速に進行』しているため、今回の入林禁止という措置になったようだ。
もう長いこと行ってないし、釣りを抜きに何時間も山を歩いたりすることはないのだけど、芦生の森にはまたいつか行ってみたい。魚を釣ることができなくても、ネイティブのヤマメやイワナ(イワナはまだ源流に集落があったときに滋賀県側から持ち込まれ、放流されたらしい)の存在を感じながら川沿いの山道を歩くのはきっと楽しいはずだ。
■芦生研究林HP
■京都新聞 滋賀県側からの入山禁止 京大芦生研究林 森林破壊や遭難防止へ
大きな虫眼鏡を手にした講師の久山喜久雄さんを先頭に、30組の親子が虫や植物に目をこらしながらゆっくりと山道を歩いた。息子はもちろんだけど、母親も冬虫夏草のクモタケ(蜘蛛から生えてます)を見つけたりして楽しんだみたい。
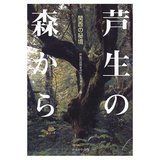 ところで、昨日の京都新聞に美山にある京大の芦生研究林(演習林から呼び名がかわった)の滋賀県側からの入山が禁止になったという記事が載っていた。
ところで、昨日の京都新聞に美山にある京大の芦生研究林(演習林から呼び名がかわった)の滋賀県側からの入山が禁止になったという記事が載っていた。滋賀県、福井県との県境に広がる芦生の森は大正10年から京大の演習林として使用されている広大な原生林だ。
由良川の源流部に自然の森が広がっている。下流部に事務所があって入山者の管理をしているのだが、演習林の北東にあたる滋賀県との県境にある地蔵峠からも入山できるようになっていた。かっては地蔵峠の手前まで車でいくことができた(数年前に峠のずっと手前にゲートが設置されそこから30分ほど歩いて峠を越えるようになったらしい)。もう10年近く前のことだが、ボクは何度かそこから演習林にはいり、由良川の源流にそって1時間位歩いたところから、釣りをしたことがある。
何度か釣り雑誌でも見たことがあるし、わりと有名な釣り場だったのだけど、釣り場まで最低でも1時間は歩かないとたどりつかないので、京都府内では珍しく春先を過ぎても魚が残っていた。
しかし、釣りをしながらもなんとなくここで釣りをしても大丈夫なのだろうかという心配はあった。まったくの手つかずというわけではないけれど、しっかりと管理され守られている森を守ったほうがいいのではないかという思いは持っていた(もちろんそれよりも魚を釣りたい気持ちの方が強かったから1時間も山道を歩いたのだが・・・)。
釣り人だけではなく、山歩きでの入林ももちろん多く、『入林者の増加に伴う歩道(周辺)の拡大と踏み固めにより、森林の荒廃が急速に進行』しているため、今回の入林禁止という措置になったようだ。
もう長いこと行ってないし、釣りを抜きに何時間も山を歩いたりすることはないのだけど、芦生の森にはまたいつか行ってみたい。魚を釣ることができなくても、ネイティブのヤマメやイワナ(イワナはまだ源流に集落があったときに滋賀県側から持ち込まれ、放流されたらしい)の存在を感じながら川沿いの山道を歩くのはきっと楽しいはずだ。
■芦生研究林HP
■京都新聞 滋賀県側からの入山禁止 京大芦生研究林 森林破壊や遭難防止へ